相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。

一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

佐藤 智春
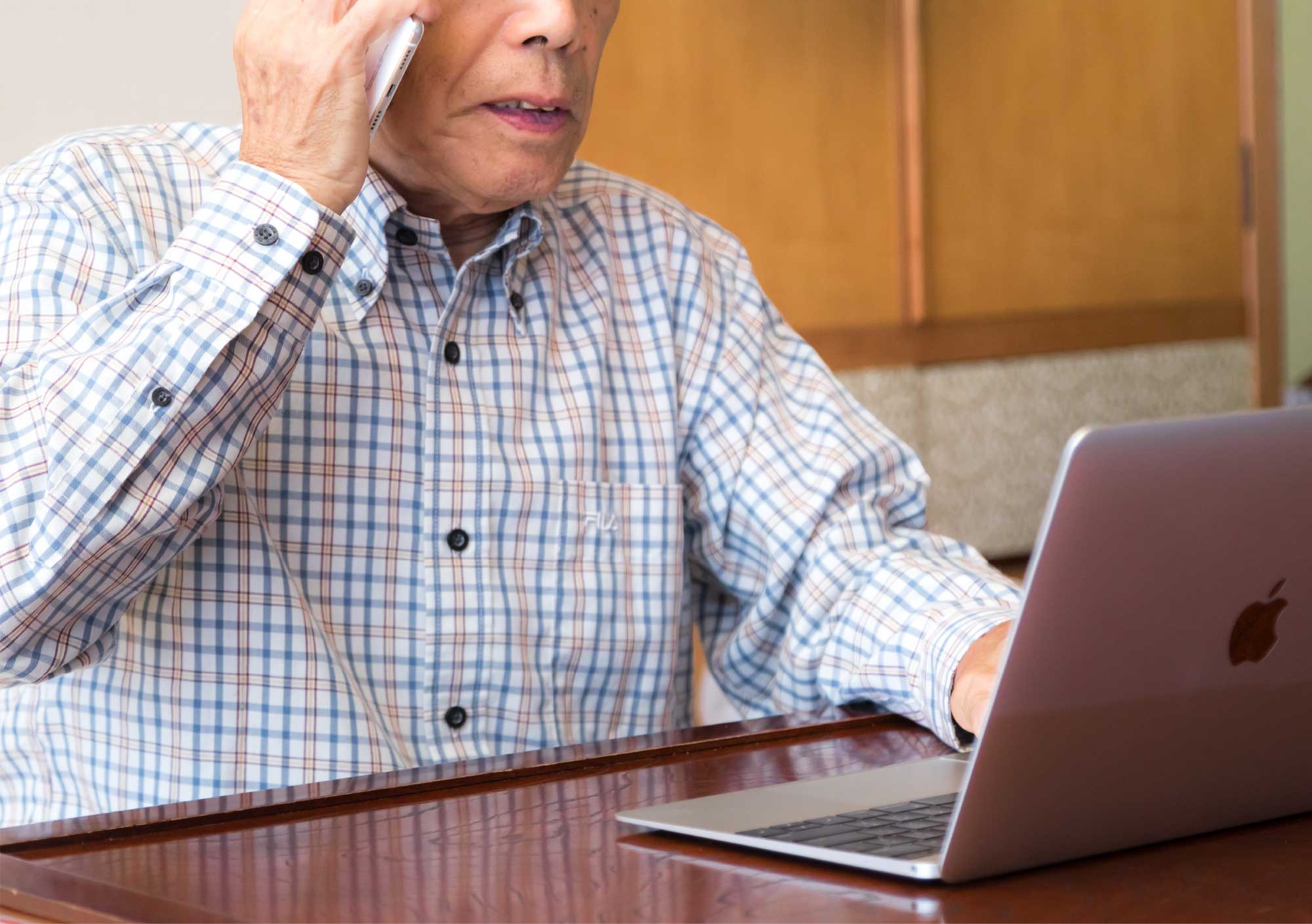
相続や贈与は「まだ先の話」と感じる人も多いかもしれませんが、高齢化が進む現代では、生前の財産対策として真剣に考えるべき重要なテーマとなっています。中でも注目されるのが「相続時精算課税制度」です。この制度は、2,500万円までの贈与について贈与税が非課税になるという特徴から、節税目的で関心を持たれることが多い一方で、制度の仕組みをよく理解せずに利用すると、逆に損をしてしまうこともあります。
相続時精算課税制度は、生前贈与を検討している方にとって魅力的な選択肢となる制度であり、2024年(令和6年)からは新たに年間110万円の基礎控除が導入され、従来よりも使いやすくなりました。ただし、一度選択すると元には戻せないといった注意点もあり、制度の仕組みや適用条件、活用のタイミングをしっかりと理解することが大切です。
この記事では、相続時精算課税制度の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、制度を活用する際の注意点までを、できる限りわかりやすくご紹介します。
まずは、この制度がどのような背景で生まれ、何を目的としたものなのかを押さえておきましょう。制度の仕組みを正しく理解すれば、自分にとって使う価値があるかどうかを冷静に判断できるようになります。

制度の概要
相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に利用できる制度です。贈与総額2,500万円までは贈与税がかからず、超えた分には一律20%の贈与税がかかります。2024年からは新たに年間110万円の非課税枠も追加され、さらに使いやすくなりました。ただし、贈与した財産は相続発生の際、相続財産に加算され、相続税の対象となる点に注意が必要です。
利用の条件
贈与者:その年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母
受贈者:18歳以上の子または孫(2022年4月以降、18歳に引き下げ)
対象財産:現金、不動産、有価証券など、多様な財産が対象
暦年贈与との違い
暦年贈与は、年間110万円までの贈与に贈与税がかからない制度で、毎年自由に贈与できます。一方、相続時精算課税制度は贈与額にかかわらず申告が必要で、生涯2,500万円まで非課税ですが、贈与財産は相続時に相続財産として加算される点が大きな違いです。
相続時精算課税制度
非課税枠:生涯で2,500万円+年間110万円(2024年以降)
税率:超過分に一律20%
相続時の扱い:原則、贈与財産を相続財産に加算(基礎控除分除く)
申告の要否:基礎控除超過分のみ申告必要(基礎控除内は不要)
選択後の変更:不可
相続時精算課税制度は、2024年から年間110万円までの贈与が非課税となり、相続財産への加算も不要になりました。この非課税枠は2,500万円の特別控除とは別枠で適用されます。制度選択後でも110万円以内の贈与は申告不要で、少額贈与を気軽に行えるなど制度の使い勝手が大きく向上しました。
暦年贈与
非課税枠:年間110万円
税率:最大55%(累進課税)
相続時の扱い:一定条件下で加算不要
申告の要否:110万円以下なら申告不要
選択後の変更:毎年選択可能
2024年以降、暦年贈与は相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるようになり、従来の3年から加算対象期間が延長されました。
制度の「非課税」という一面だけを見ると魅力的に映りますが、実際には「相続時に課税が先送りされる制度」であるということをしっかり理解しておく必要があります。特に、一度選択すると暦年贈与には戻れないという点は、贈与を検討する際の大切なポイントとなります。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
相続時精算課税制度を利用すべきかどうかは、個々の家庭の状況や財産の種類・額に大きく左右されます。その判断のためには、制度の長所と短所を客観的に把握しておくことが不可欠です。ここでは代表的なメリットとデメリット、そして制度を選択すべき典型的なケースについてご紹介します。

制度利用のメリット
2,500万円+110万円まで非課税で贈与できる
令和6年から導入された年間110万円の基礎控除により、贈与税の負担がさらに軽減されました。非課税の枠は、生涯で2,500万円+毎年110万円と考えることができ、非常に大きな節税効果が期待できます。
一律20%の税率で贈与が可能
非課税枠を超えた場合でも、通常の贈与税(最大55%)に比べ、税率が一律20%と低く抑えられています。たとえば、3,000万円の贈与でも、課税対象は490万円(3,000万円-2,500万円-110万円)にとどまり、税負担が軽く済みます。
好きなタイミングで自由に贈与できる
暦年贈与のように年ごとの制限がなく、自由なタイミングで財産を移転できます。現金、土地、建物、有価証券など、多様な資産が対象となるため、柔軟な資産移転が可能です。
収益財産の早期移転が可能
賃貸アパートや駐車場などの収益を生む財産を早めに子や孫に移転することで、贈与者の課税所得を抑えると同時に、受贈者に収益を渡すことができます。これにより、家族間での資産活用の幅が広がります。
生前の財産分割ができる
相続時のトラブルを避けるためにも、「自宅は長男へ」「預貯金は次男へ」といったように、特定の財産をあらかじめ指定して贈与することができます。
制度利用のデメリット
相続時に再度課税対象になる
制度名の通り、最終的には相続時にすべての贈与が再計算され、相続税の課税対象となります。生前に贈与したからといって節税になるとは限らない点に注意が必要です。
暦年贈与には戻れない
いったん相続時精算課税制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については、以後ずっとこの制度が適用されます。柔軟な贈与戦略が取りにくくなります。
毎年の贈与税申告が必要
110万円以下の贈与は申告不要ですが、それを超える場合は、たとえ非課税枠内でも毎年の申告が必要です。忘れてしまうとペナルティの対象となる可能性もあります。
不動産の贈与には諸費用がかかる
登記費用、登録免許税、不動産取得税など、別途発生するコストも考慮する必要があります。
この制度は、状況によっては非常に有効な手段となる一方で、内容をよく知らずに使うと「思ったより税金がかかった」「不利だった」という結果にもなりかねません。制度の仕組みや制約をしっかりと理解したうえで、自身や家族のライフプラン・資産状況に合った選択をすることが重要です。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
相続時精算課税制度を効果的に活用するには、事前にいくつかの重要なポイントを押さえておくことが大切です。以下の注意点を参考にしながら、制度の選択が本当に自分や家族にとって有利かどうかを検討しましょう。

暦年贈与との違いを十分理解する
暦年贈与は年間110万円まで非課税で、贈与する年を選べば税金がかからないという柔軟性があります。一方、相続時精算課税制度は一度選択するとその贈与者に対して撤回できず、相続時には課税されるため、長期的な視点が必要です。
基礎控除110万円の使い方を誤らない
令和6年から導入された新しい110万円の基礎控除は、相続時に持ち戻しされず、贈与税申告も不要となります。しかし、この基礎控除は暦年贈与とは併用できません。両制度の控除を混同しないよう注意しましょう。
特定の人への偏った贈与はトラブルのもとに
たとえば、同居している子にだけ土地や家を贈与すると、他の相続人から「不公平だ」と見なされ、相続時に特別受益として問題になる可能性があります。贈与の配分や内容については、家族間でよく話し合い、必要に応じて遺言書の活用なども視野に入れましょう。
財産の将来価値も見極める
評価額が将来的に上がると見込まれる不動産や株式などは、早めに贈与しておくことで、相続時に加算される評価額を抑えられる可能性があります。反対に、価値が下がる可能性のある資産を早く贈与してしまうと、結果的に損をするケースもあります。
相続税申告時に漏れに注意!?
相続時精算課税制度を利用したことが相続税申告時に漏れ、税務署から指摘を受けるケースがあります。過去の贈与の把握漏れや記録不備が原因となりやすく、誤りがあると追徴課税の可能性もあるため、申告時には制度の利用状況を確認し、専門家に相談することが大切です。
相続時精算課税制度を効果的に活用するためには、制度の基本をしっかり理解し、注意点を押さえたうえで、家族や財産の状況に最適な戦略を立てることが不可欠です。
相続の専門家などの助言を受けながら、制度の利用条件やコスト、申告義務を正しく理解し、自分や家族にとって最適な選択をすることで、将来の相続に備えることができます。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。
最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。
しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。
だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。
相続時精算課税制度は、一見すると「2,500万円まで贈与税ゼロ」というメリットばかりが強調されがちですが、その本質は「課税の先送り」です。加えて、令和6年から新設された110万円の基礎控除によって、制度の利便性が高まる一方、判断の複雑さも増しています。
制度の選択は、家族構成や財産の内容、今後のライフプランなどを総合的に考慮して行う必要があります。「節税になるから」と安易に飛びつくのではなく、税理士などの専門家に相談しながら、自分たちにとって本当に有益な方法を選びましょう。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中