相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。

一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

佐藤 智春

「相続について調べよう」と思ったとき、まずGoogle検索やAI(人工知能)で情報を集める方が増えています。最近では、検索結果の上に表示される「AIによる概要(AI Overview)」や、ChatGPTなどの生成AIの回答を参考にする人も多いでしょう。確かにAIは便利で短時間に答えを返してくれますが、相続のように法律や税制が絡む分野では「その情報が正しいとは限らない」というリスクがあります。
AIの情報は誤りや古い内容が混ざっている場合があり、そのまま従ってしまうと多額の追徴課税や親族間のトラブルにつながる恐れがあります。本記事では、「GoogleやAIを使った相続対策の落とし穴」と「正しい知識を得るために専門家に相談すべき理由」を税理士法人の視点から徹底解説します。AI時代においても失敗しない相続対策を知りたい方はぜひ最後までお読みください。
AIが生成する回答やGoogle検索結果は、一見すると便利で正確な情報源のように思えます。しかし実際には、相続分野で誤りや不正確な情報が多いのが現状です。2024年にGoogleがリリースした「AI Overview」では、「ピザにチーズを接着剤で貼り付ける」といった“珍回答”がSNSで話題になりました。こうした不具合に対し、Google側も修正対応を進めていますが、現時点でAIはまだ完璧なものとは言えません。
特に税制や法律が関わる相続は、情報の小さな間違いが重大なトラブルや予期せぬ税負担につながるリスクがあります。ここでは、なぜAIやGoogleの情報に「間違いが多い」のか、そしてその背景を詳しく解説します。

AIやGoogleの誤情報の背景
1. AIは「正しい情報」だけを返すわけではない
AIは膨大なインターネット上の情報を学習し、回答を生成しています。しかし、元の情報が誤っていれば、当然AIの出力も間違います。さらに相続分野は法律・税制改正が頻繁に行われるため、古い知識がそのまま引用されるケースも少なくありません。
2. Google検索の上位記事も正確とは限らない
Google検索の上位に表示される記事は、多くの場合SEO対策によって順位が決まっています。つまり、専門家が監修した正確な内容とは限らないのです。特に個人ブログや情報まとめサイトでは、根拠が不十分な内容が掲載されていることも多く、注意が必要です。
3. 個別事情はAIにはわからない
相続手続きは、家族構成・財産内容・地域ごとのルールや状況によって大きく異なります。しかし、AIはこうした個別事情を考慮できません。たとえば、相続税の配偶者控除についてAIに質問すると、一般的な答えは得られるものの、実際の家族構成や資産状況に応じた正確なアドバイスは期待できません。
4. 例:相続分野でのAIの誤回答
AIやGoogleの生成情報の中には、「小規模宅地等の特例は誰でも使える」といった誤ったアドバイスが含まれていることがあります。こうした情報を鵜呑みにしてしまえば、適用要件を満たさず特例が認められないリスクや、多額の追徴課税につながる恐れがあります。
AIやGoogle検索は、情報収集の「入り口」としては有用です。しかし、相続や税務は専門性が非常に高い分野であり、個別事情に応じた正確な判断が欠かせません。間違った情報に基づいて手続きを進めれば、親族間の争いや思わぬ税負担が発生することもあります。
相続対策や税務申告は、相続専門の税理士に相談することが重要です。正確かつ的確なアドバイスを受けることで、大切な資産とご家族の未来を守ることにつながります。迷ったときは、ぜひ早めに専門家へご相談ください。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
AIやGoogle検索の情報は、便利で短時間に知識を得られる反面、相続手続きの分野では大きな落とし穴になることがあります。最近では、こうした情報を頼りに相続を進めたことで、深刻なトラブルや予想外の税負担に発展するケースが増えてきました。
特に、相続は法律や税制の細かい知識が必要であり、少しの判断ミスが家族間の対立や高額な追徴課税につながるリスクがあります。ここでは、AIやGoogle情報を鵜呑みにすることで起こりえる失敗例をご紹介し、その危険性について解説します。
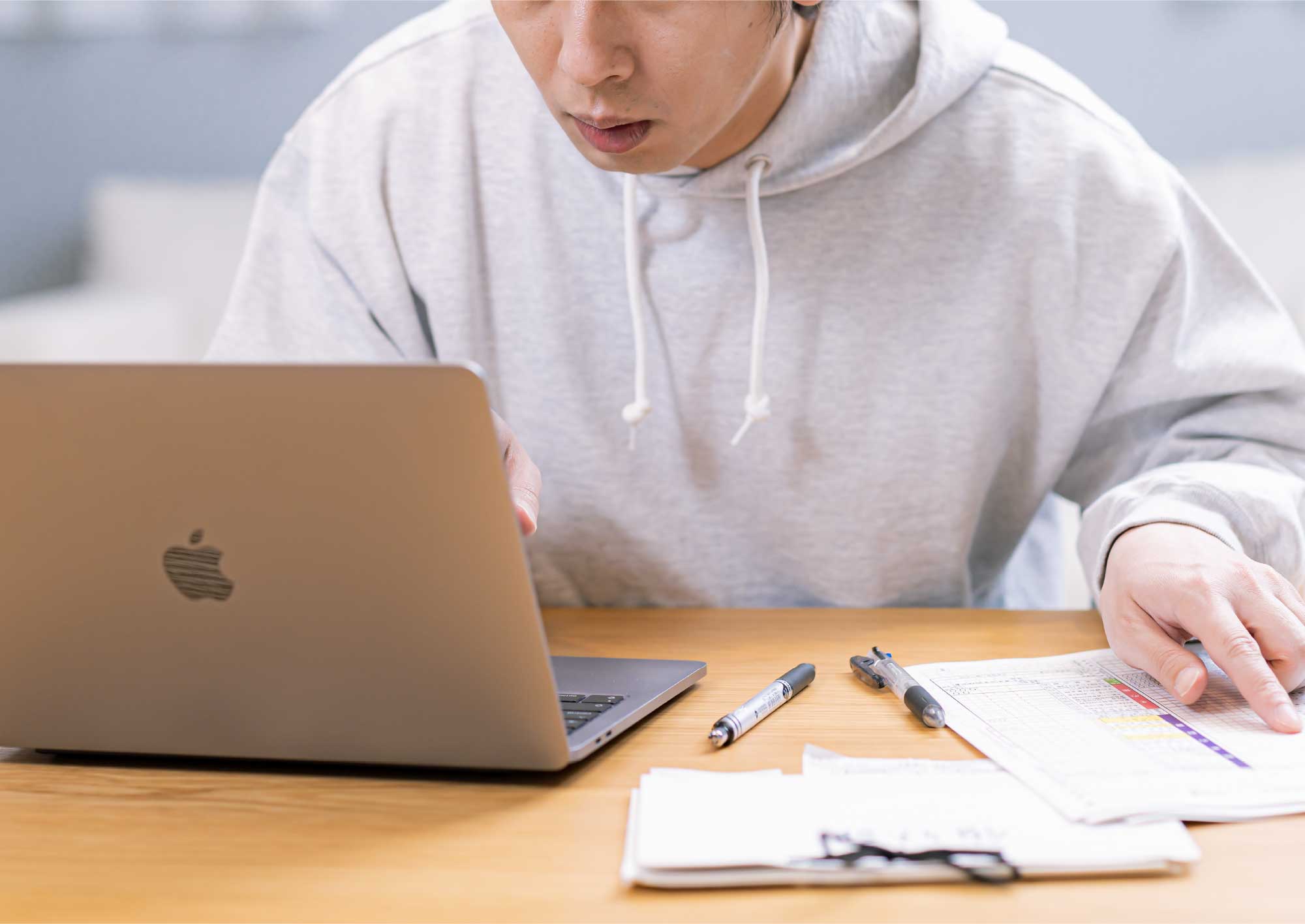
AIやGoogleの誤情報でわかりやすい失敗例
ChatGPTなどのAIを使って、自分が引き継いだ相続財産にかかる相続税を試算した方がいました。
算出された相続税額が少なかったため、「これは助かった」と安易に受け止め、そのままの金額を信じてしまいました。相続税の申告も簡単だと思い、見よう見まねで手続きを進めたところ、後日税務署から申告内容の誤りを指摘され、AIで試算した金額とは大きく異なる多額の相続税を請求されてしまいました。
相続税の申告は非常に複雑で、財産評価の誤りや特例・控除の適用ミスが起こりやすいです。そのため、適切に対応するためには相続税の専門家に相談することが大切です。
AI情報やネット検索は便利なツールですが、相続分野では「正確性」と「個別性」が不可欠です。間違った情報を頼りに手続きを進めてしまうと、親族間の争いや多額の損失を招きかねません。
相続税申告や遺産分割などの重要な局面では、相続専門の税理士や弁護士といったプロフェッショナルに相談することが何より大切です。早い段階から専門家を味方につけることで、余計なトラブルを避け、大切な家族の未来を守ることにつながります。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
相続税申告は一見シンプルに思えても、実際には専門知識がなければ間違えやすいポイントが多い非常に繊細な手続きです。誤った申告は、追徴課税や高額な税負担、さらには家族間のトラブルを引き起こす可能性があります。
ここでは、相続税申告で特に注意すべきポイントと、専門家に相談することで得られるメリットをわかりやすく解説します。

相続税申告で特に注意すべきポイント
1. 相続税の2割加算の見落とし
被相続人の配偶者や子以外の親族(兄弟姉妹、甥姪など)が相続人になる場合、相続税は2割加算されます。この制度を見落とした場合、申告内容に不備が生じ、後から修正申告や追徴課税が必要になることもあります。
2. 名義預金の見落とし
被相続人が生前、子や孫名義で管理していた預金(いわゆる名義預金)は、形式上の名義にかかわらず相続財産として計上する必要がある場合がほとんどです。これを見落とすと、税務調査で指摘を受け、追徴課税の対象となりかねません。
3. 生前贈与のカウント漏れ
亡くなる直前の贈与にも注意が必要です。被相続人が亡くなる**3年以内(令和6年以降は7年以内)**に行われた贈与は、相続財産に加えて課税されます。このルールを理解せず申告すると、過少申告としてペナルティの対象になることがあります。
4. 土地評価のミス
土地の評価は、相続財産の中でも特に難易度が高い項目です。路線価方式や倍率方式などの計算が複雑で、少しの誤りが数百万円単位の税額の差につながることもあります。
5. 特例の適用漏れ
「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」など、相続税を大幅に軽減できる特例は複数あります。しかし、適用要件の確認や申告書への正しい記載が必要で、知識不足から適用を漏らすと、本来払わなくてよい税金を過払いするケースも少なくありません。
6. 専門家に相談するメリット
相続税申告は、税理士などの専門家の助言を得ることで、次のような大きなメリットが期待できます。
税務調査リスクを軽減
税理士が関与することで、申告書の信頼性が高まり、税務署による調査対象になりにくくなります。
適切な特例適用で納税額を最小化
専門知識を活かして最大限の節税策を講じてもらえます。
二次相続を見据えた節税アドバイス
現在の相続だけでなく、将来の二次相続に備えたアドバイスが受けられます。
相続税申告は、専門家のサポートがあるかどうかで結果が大きく変わる手続きです。誤った判断や情報不足が後々大きな負担となる前に、ぜひ相続に強い税理士へ相談しましょう。
早い段階からプロのアドバイスを受けることで、大切な財産を守り、家族の未来を安心して託すことができます。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。
最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。
しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。
だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。
AIやGoogle検索は確かに便利で、ちょっとした調べ物には役立つツールです。しかし、相続のように複雑な分野では、小さな間違いが取り返しのつかないトラブルや高額な税負担に発展するリスクがあることを忘れてはいけません。特に相続税申告は、家族構成や財産内容によって必要な手続きが大きく変わるため、正確で個別事情に即した判断が求められます。
みらいえ相続グループでは、相続税申告・節税対策・遺産分割・事業承継など、相続に関するあらゆるご相談に対応しています。専門の税理士・スタッフがあなたの状況に合わせた最適なアドバイスをご提供し、トラブルや無駄な税負担を未然に防ぎます。
大切な資産を守り、ご家族の未来を安心してつなぐためにも、早めに専門家へ相談することが何より重要です。みらいえ相続グループの初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中