相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。

一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

佐藤 智春

遺産相続に関するご相談で、よくいただく質問のひとつに
「相続した翌年に確定申告は必要ですか?」 というものがあります。
結論としては
「相続税の申告は必要ですが、確定申告は原則不要」 です。
相続財産が一定額を超える場合、相続税を支払う義務が発生しますが、相続そのものによって確定申告をする必要はありません。ただし、特定のケースでは確定申告が必要になることもあるため、注意が必要です。
そもそも相続税と所得税にはどのような違いがあるのでしょうか。相続税と所得税はどちらも税金ですが、それぞれ課税の目的や対象が異なります。
相続税
財産を無償で受け取ることに対して課税される税金です。相続によって財産を受け継いだ場合に適用されます。
所得税
給与や年金などの収入を得ることに対して課税される税金です。働いて得た給与などが対象となります。
このように、相続によって財産を受け取っただけでは所得税の対象にはなりません。 ただし、相続した財産を売却した場合や、その財産が一定の収益を生む場合には、所得税の申告が必要になることもあります。
相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。手続きには財産の調査や遺産分割協議などが含まれるため、早めの準備が重要です。

相続税申告の主な流れ
期限3カ月以内
遺言書の確認 / 相続人の確定 / 相続放棄・限定承認の手続き
期限4カ月以内
被相続人の準確定申告(所得税の申告)
期限10カ月以内
財産・債務の調査・評価 / 遺産分割協議 / 名義変更 / 相続税申告・納付
相続財産は所得税ではなく相続税の対象ですが、家賃収入や配当などの収益が発生した場合や、相続財産を売却して利益が出た場合など、被相続に代わって確定申告を行う「準確定申告」と相続人が財産を引き継いだ後の確定申告を行う必要ある場合があります。そのため、相続時には確定申告が必要かどうかを事前に確認することが重要です。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
相続財産に対して所得税は原則かかりませんが、相続後に確定申告が必要となるケースがあります。
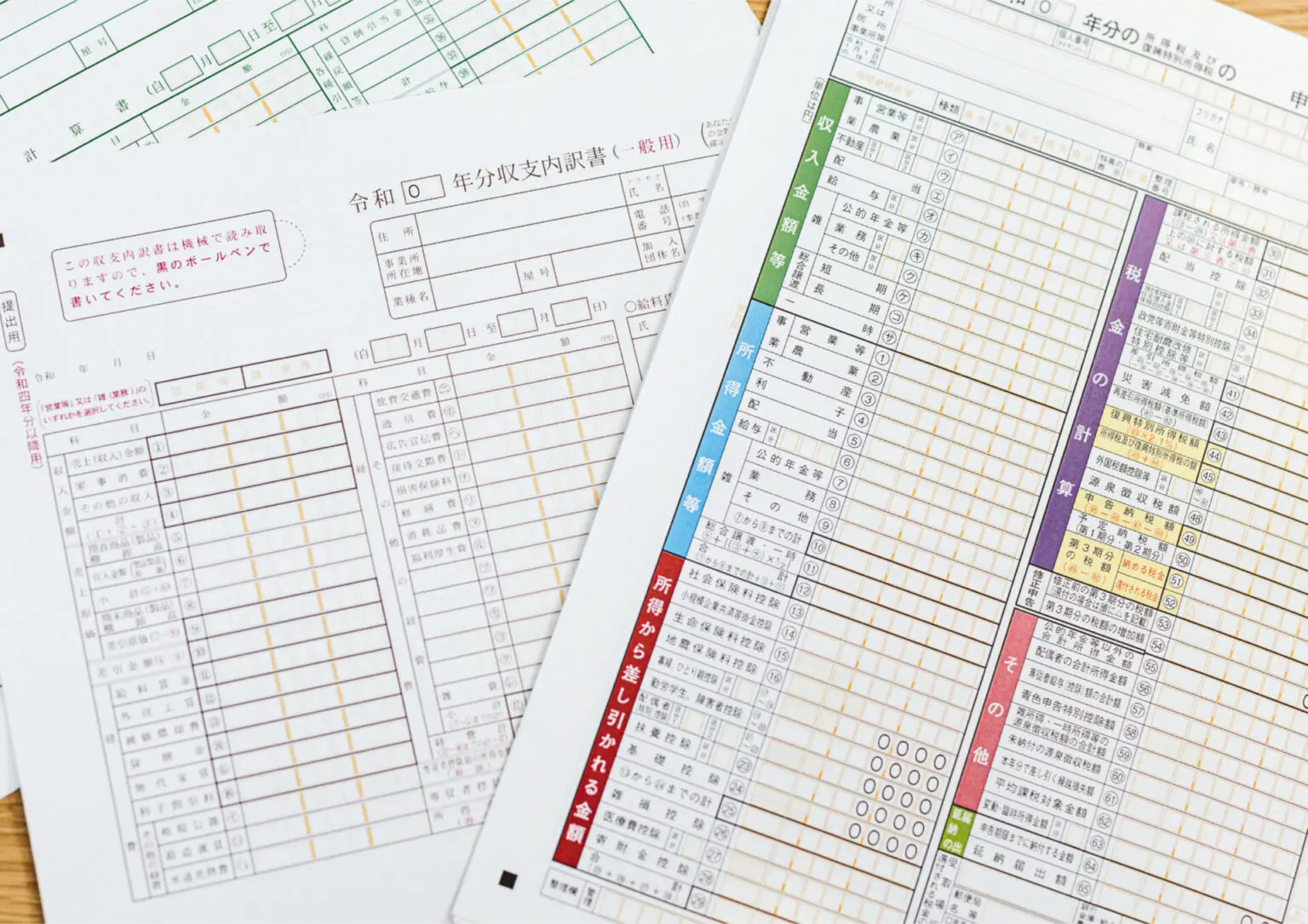
相続人自身が確定申告をする必要がある例
相続そのものでは確定申告は不要ですが、相続した財産を売却したり、賃料収入を得た場合は所得税の申告が必要になります。
相続財産を売却した場合
相続した不動産や株式などを売却し、売却益(譲渡所得)が発生した場合は、その利益に対して所得税が課されます。売却した翌年に確定申告を行う必要があります。
相続したアパートなどの収益物件から賃料を得た場合
相続したアパートや貸家などの収益物件から賃料収入を得る場合、その家賃収入は相続人の所得として扱われます。そのため、翌年に所得税の確定申告をする必要があります。
被相続人の代わりに確定申告(準確定申告)をする必要がある例
被相続人(亡くなった方)が生前に所得税の申告義務があった場合、その未申告分を相続人が申告する必要があります。これを 「準確定申告」 といいます。
準確定申告とは?
被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、相続人が代理で確定申告を行う制度です。例えば、亡くなった方に事業所得や家賃収入があった場合、本来は確定申告が必要ですが、ご本人が申告できないため、相続人が代わりに行います。相続開始(亡くなった日)の翌日から4か月以内に、所轄の税務署へ申告・納税をしなければなりません。
相続税の申告・納付は手間がかかるうえ、相続人自身の確定申告や準確定申告が重なると、すべてを自分で対応するのは大きな負担になります。少しでも不安を感じたら、早めに税理士へ相談しましょう。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。
最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。
しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。
だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。
税金や申告の種類によって対応方法は異なり、特に相続に関する申告は複雑です。正しく手続きを進めるために、以下のポイントを押さえておきましょう。
1. 申告義務の有無を確認
相続税や所得税の確定申告が必要かどうかを判断します。特に、相続財産が一定の金額を超える場合や、被相続人(亡くなった方)に未申告の所得があった場合は、申告が必要になる可能性があります。
2. 必要な情報の収集・整理
相続財産の種類や金額、負債の状況を把握し、申告に必要な書類を準備します。具体的には、以下のような情報を整理します。
預貯金や不動産の評価額
株式や投資信託の価値
借入金や未払いの税金
3. 適用できる特例や控除の検討
相続税にはさまざまな特例や控除があり、適用することで税負担を軽減できる場合があります。例えば、小規模宅地等の特例や配偶者控除などが該当します。適用条件を確認し、最適な方法を選択することが重要です。
相続に関する申告は手続きが煩雑で、誤った判断をすると税負担が増えることもあるため、慎重に進める必要があります。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中