相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。

一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

佐藤 智春
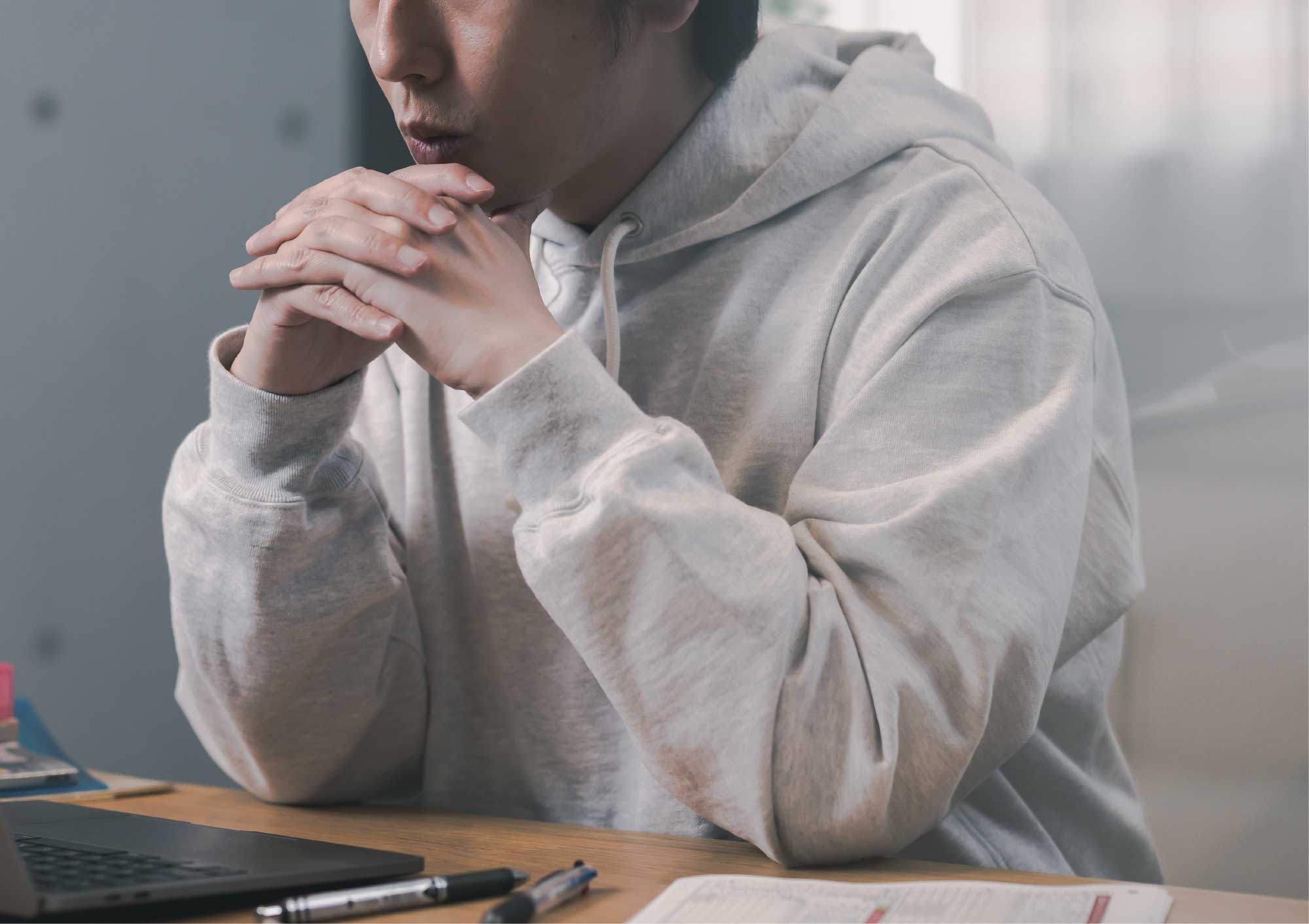
日本テレビ系で放送中の遺産相続ドラマ「相続探偵」の第8話が放送されました。物語もいよいよ終盤に差し掛かり、相続をめぐる複雑な人間模様がより深く描かれています。登場人物たちが抱える過去や信念が交錯し、予測不能な展開へと進んでいく本作。
今回のテーマは、前回に続き「死後認知」と、新たに「家族の在り方」が大きな鍵を握ります。血のつながりとは何か?法的な相続関係だけでは割り切れない思いが交錯する中、主人公・灰江七生が導き出した答えとは。今回もドラマの展開を追いながら、相続にまつわるポイントとともに詳しくご紹介していきます。
亡くなった東大名誉教授・薮内晴天の隠し子疑惑を晴らした灰江七生(通称ハイエナ)。しかし、8人目の隠し子を名乗る青年・島田正樹(小林虎之介)が現れます。母の死の間際に「父は薮内教授」と聞かされましたが、証拠は一枚の写真のみでした。
DNA鑑定の結果、正樹が薮内の実子である可能性が高いと判明します。さらに、薮内が正樹の実家のローンの連帯保証人だったことも分かり、関係はより確実なものとなります。一方、記者の羽毛田は正樹の情報を入手し、スクープを狙っていました。
第8話の序盤、正樹は「死後認知の訴えを起こさず、解決金も受け取らない」と決断します。それは、母の笑顔を守りたいという思いからでした。しかし、薮内の妻・佐賀美は全遺産を正樹に譲り、この事実を公表すると言い出します。灰江は「家族の思い出は家族のもの」と諭し、佐賀美に公表はしない方が良いと説得します。
一方、羽毛田は末期ガンで余命3カ月を宣告され、人生を見つめ直しはじめます。そして翌日、週刊誌に「8人目の隠し子」の記事が掲載され、正樹の家にマスコミが殺到。灰江は激怒し、出版社へ乗り込もうとするのでした。
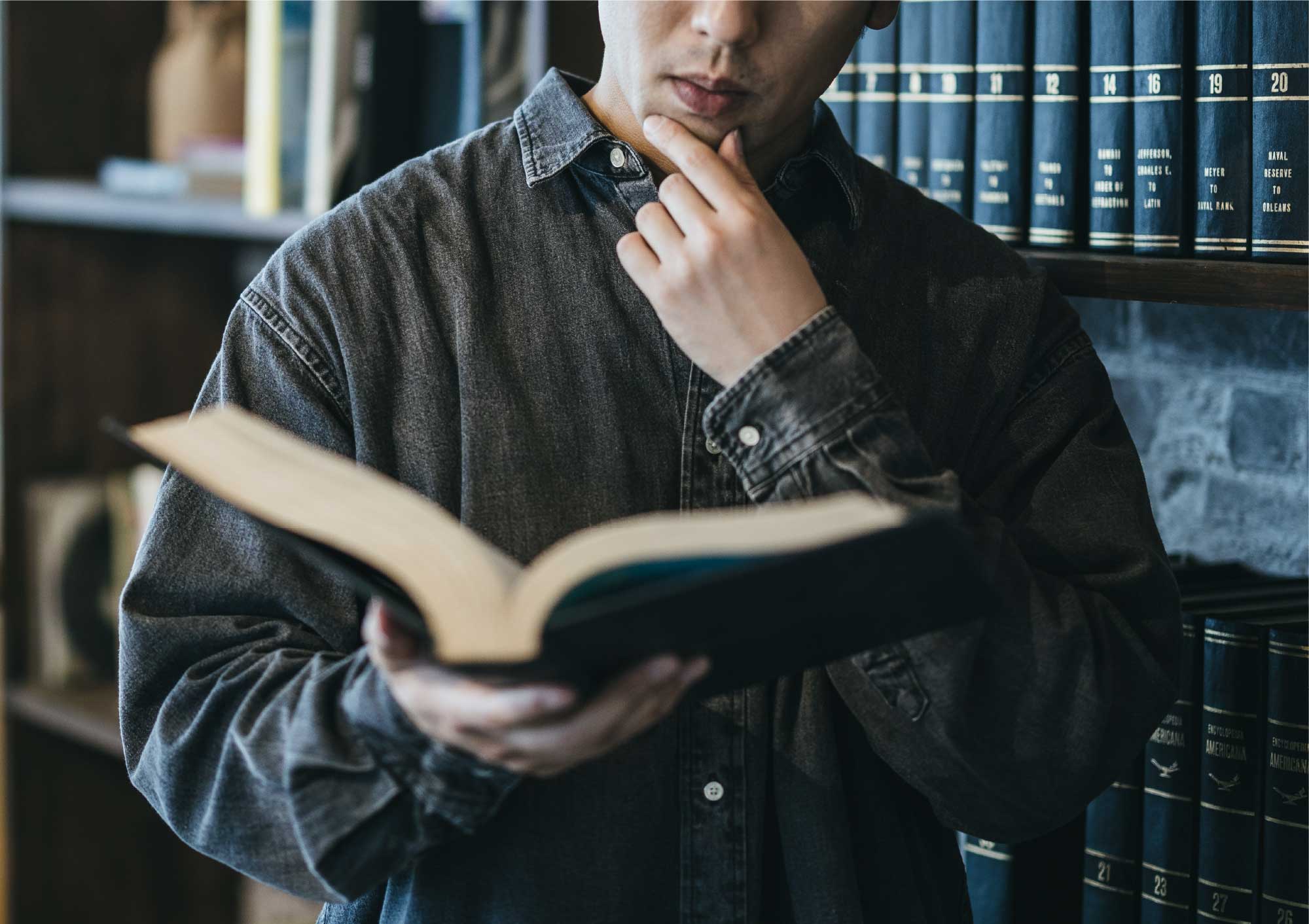
視聴者の疑問「家族が納得し相続するためにはどうすれよいの?」
専門家の回答「事前の準備と話し合いをしっかり行いましょう。」
「家族の思い出は、プラスもマイナスも、やっぱり家族のものだけでいいと思うんです。」この言葉は、物語の序盤で主人公・灰江の価値観を象徴する重要なセリフです。
相続においても、単に財産を分けることが目的ではなく、故人の意思と家族の想いを尊重し、全員が納得できる形で解決することが理想的です。相続に関するトラブルを避けるためには、事前の準備と話し合いが不可欠です。
ここでは、円満な相続を実現するために必要な具体的な対策を紹介します。
1. 遺言書の作成
相続争いを防ぐため、遺言書の作成は不可欠です。公正証書遺言は、公証人が関与するため法的効力が高く、偽造や紛失のリスクがありません。一方、自筆証書遺言は自分で作成できますが、形式を満たさなければ無効となる可能性があります。
2. 家族会議の実施
相続を円満に進めるためには、事前に家族全員で話し合うことが重要です。特に不動産や事業継承が絡む場合、誰が何を受け継ぐのかを明確にしておくことで、相続争いを未然に防ぐことができます。話し合いの際には、感情的な対立を避けるために、税理士などの第三者を交えるのも有効です。
3. 生前贈与の活用
生前に財産を贈与することで、相続発生時の税負担を軽減することが可能です。例えば、年間110万円までの贈与は非課税となるため、計画的に活用するとよいでしょう。また、住宅取得資金や教育資金に関する特例を利用すれば、それぞれ最大1,000万円〜1,500万円まで非課税で贈与できます。さらに、相続時精算課税制度を活用すると、2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に精算される形になります。
4. 相続税対策
相続税の負担を軽減するためには、適切な控除制度を活用することが重要です。たとえば、配偶者控除を適用すれば、配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで非課税となります。また、小規模宅地の特例を利用すると、被相続人が住んでいた土地の評価額を最大80%減額できるため、大幅な税負担の軽減が可能です。
5. 家族信託の活用
認知症対策として家族信託を活用するのも有効です。認知症になった場合、本人が資産管理を行うことが難しくなり、家族が財産を動かせなくなるリスクがあります。家族信託を利用すると、信頼できる家族(受託者)に資産管理を任せることができ、将来のトラブルを防ぐことができます。
家族が納得する相続を実現するためには、事前の準備と話し合いが不可欠です。遺言書の作成、家族会議の実施、生前贈与や相続税対策など、適切な手続きを取ることで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
また、家族の状況によって最適な方法は異なるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。相続は、一人ひとりの人生や価値観が反映される大切な問題です。納得のいく形で円満に解決するためにも、早めに準備を始めましょう。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
第8話の中盤、灰江は出版社で羽毛田と遭遇し揉み合いになりますが、弁護士・福士の介入でことなきを得ます。そして灰江は、アシスタントの令子に自身の過去を語りはじめます。
灰江の育ての父・和宏はバス会社を経営していましたが、事故で亡くなりました。強風による不慮の事故でしたが、マスコミは居眠り運転と報道。裁判も、法曹界の重鎮・地鶏健吾(加藤雅也)の圧力で判決がねじ曲げられてしまいました。実はこの地鶏こそが、灰江の実父だったのです。
灰江は育ての父の汚名をはらすため弁護士になりましたが、地鶏の悪行の証拠を掴んだ瞬間に、横領の罪をでっち上げられ資格を剥奪されたのでした。
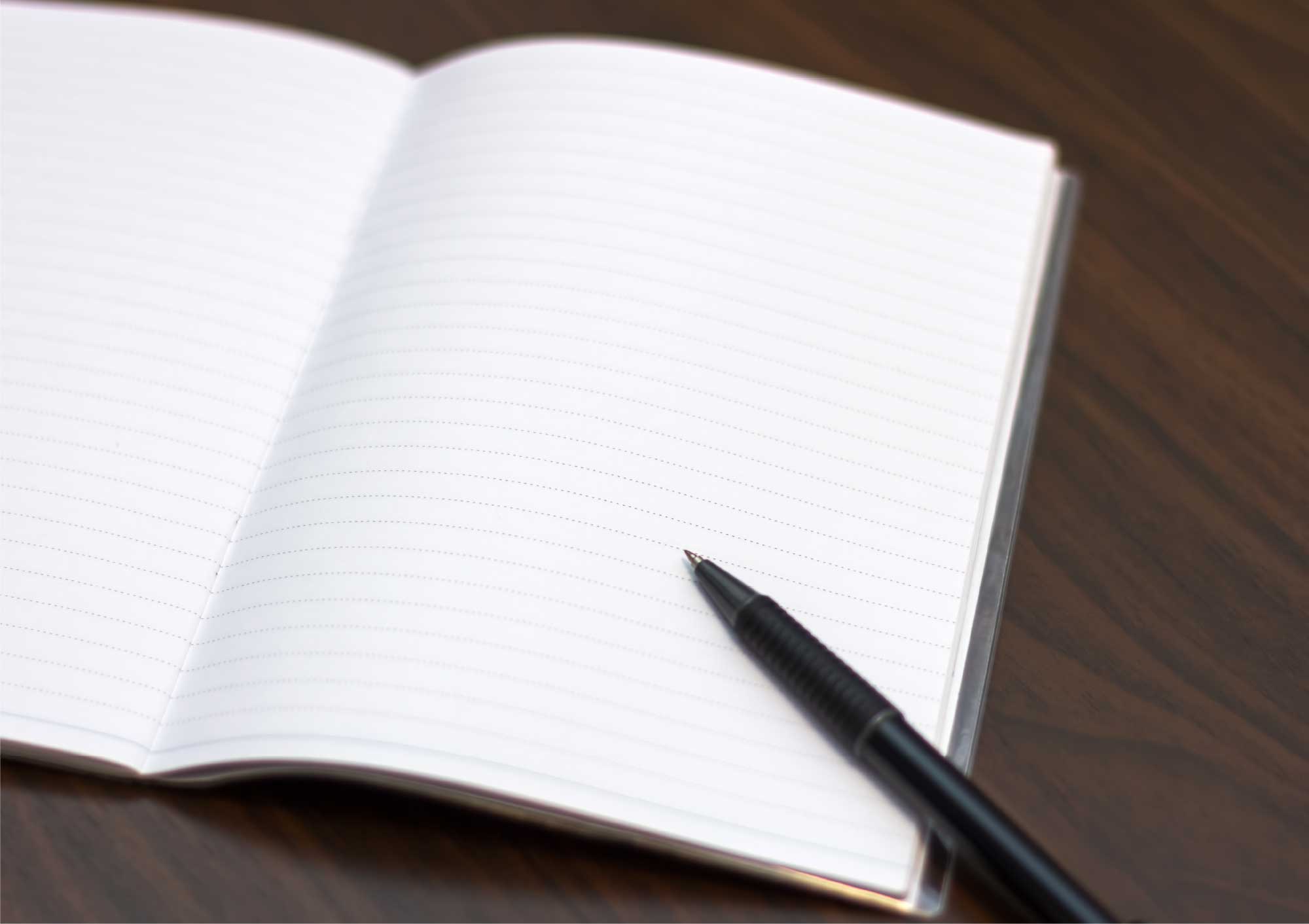
視聴者の疑問「不慮の事故で亡くなった場合、遺産はどうなるの?」
専門家の回答「遺言や法律に基づいて、相続人に引き継がれます。」
主人公・灰江の育ての父が突然のバス事故で亡くなったように、不慮の事故による突然の死は、家族に大きな精神的衝撃を与えるだけでなく、相続の問題も引き起こします。では、その場合、故人の資産はどのように扱われるのでしょうか?
不慮の事故で亡くなった場合、故人が生前に遺言書を残しているかどうかで、遺産相続の流れは大きく変わります。
遺言書がある場合
故人が遺言書を残していた場合、基本的にその内容が最優先されます。遺言書に記載された相続人や財産の分配方法に従い、スムーズに相続が進むことが一般的です。
遺言によって特定の相続人に多くの財産を残すことは可能ですが、法定相続人の遺留分(最低限の取り分)が侵害された場合、他の相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺言書があることで手続きがスムーズになる一方、内容によってはトラブルが発生する可能性もあるため、注意が必要です。
1.公正証書遺言(最も確実)
公証役場で作成。法的効力が強く、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
2.自筆証書遺言
本人が自筆で作成。家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、法務局に預けていた場合は不要です。
遺言書がない場合
遺言書がない場合、相続は民法の法定相続分に従って分配されます。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、相続人全員の合意のもとで財産を分ける必要があります。
また、故人に借金などの負債がある場合、その借金も相続の対象となります。
1.合意が得られた場合
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印することで正式に決定します。
2.合意が得られない場合
家庭裁判所での調停・審判へ進み、裁判所の判断に委ねることになります。
相続は突然発生することが多く、遺言がないと相続人同士の対立や手続きの混乱が生じる可能性があるため、トラブルを防ぐためには生前に弁護士や税理士などの専門家に相談し、遺言の作成や財産の管理を計画的に準備することが重要です。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
第8話の終盤、灰江の家族は相続放棄もできましたが、母・深雪は「逃げたくない」と全てを背負うことを決断しました。父の名誉回復のため裁判に挑みましたが敗北し、多額の賠償を負うことになります。
「母は自分がいなければ幸せだった」と自責する灰江に、令子は「母親は子どもを一番に思う」と諭し、「生まれてきてくれてありがとう」と伝えます。
灰江は父の汚名をそそぐことを決意し、墓前で手を合わせます。母と再会し「あなたが元気でいるだけで幸せ」と諭されますが、その決意は変わりませんでした。
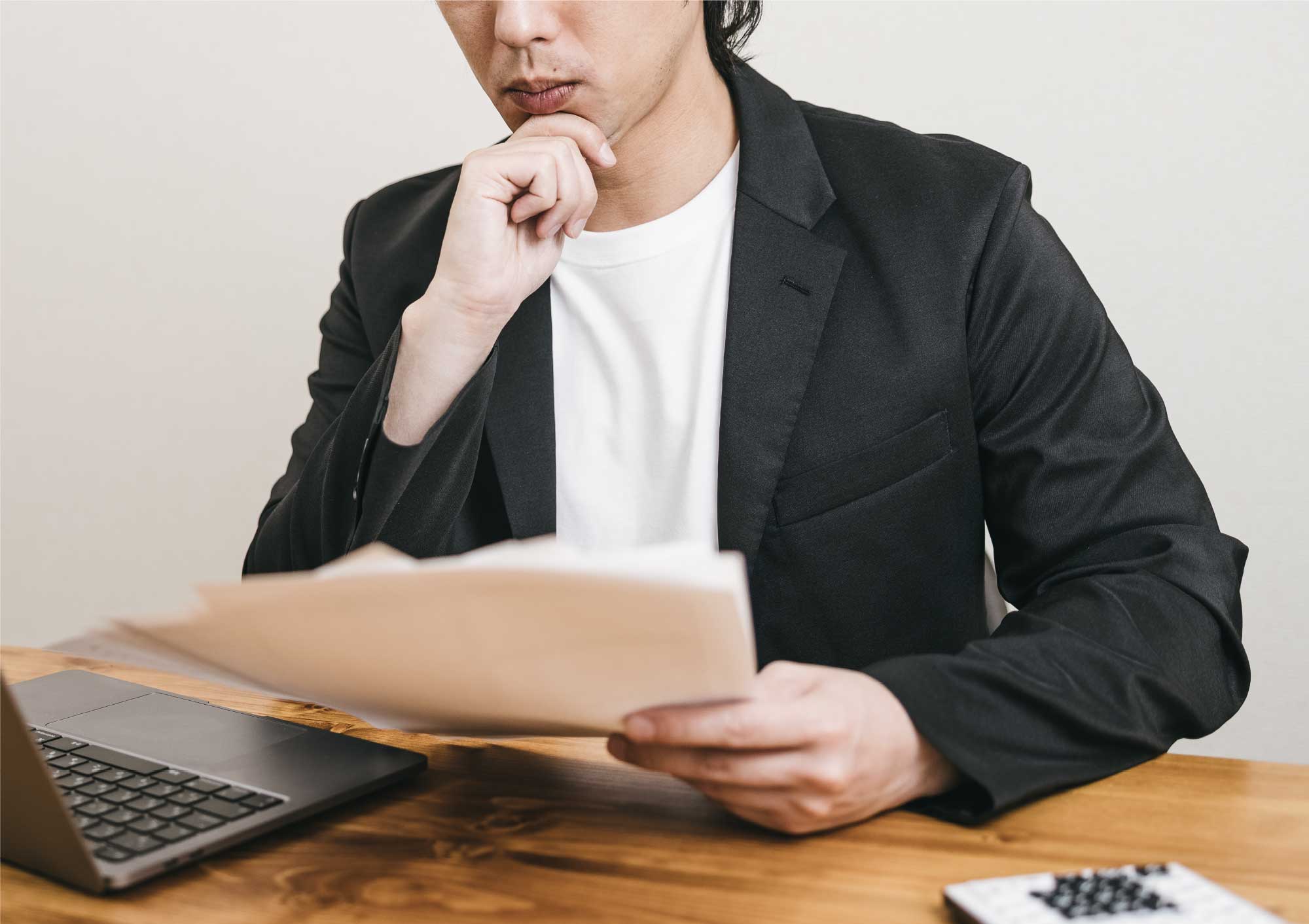
視聴者の疑問「故人に多額の借金がある場合はどうなるの?」
専門家の回答「相続放棄など早めの対応をおすすめします。」
相続は、財産だけでなく、故人が抱えていた負債(借金)も引き継がれる可能性があります。しかし、法律上は相続放棄をすることで、負債を引き継がずに済む選択肢もあります。ここでは、相続放棄の仕組みや注意点について詳しく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産や負債を一切引き継がない制度で、家庭裁判所に申し立てることで実行されます。相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされ、財産も負債も受け取る権利を失います。
相続放棄の流れ
1.財産と負債を確認
まずは、故人の財産と負債の状況を把握します。負債の方が多い場合、相続放棄を検討する必要があります。
2.家庭裁判所に申し立て
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申立書を提出します。
必要書類として、被相続人の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本、申立書などが求められます。
3.家庭裁判所の審査を受ける
裁判所から照会書(質問書)が送付されることがあり、これに回答すると、相続放棄が正式に認められます。
4.相続放棄の確定
裁判所から受理通知が届き、これにより相続放棄が法的に確定します。
相続放棄の注意点
1.期限は3カ月以内
相続放棄は、相続が発生したことを知った日から3カ月以内に手続きをしなければなりません。この期間内に財産と負債の状況を把握し、相続するか放棄するかを判断する必要があります。
期限を過ぎると、相続放棄ができなくなり、自動的に相続を承認したものとみなされるため注意が必要です。
2.単純承認をしない
相続放棄をする前に、相続財産を処分したり、借金を一部でも返済すると、放棄が認められなくなる可能性があります。
例えば、故人の預金を引き出したり、不動産を売却したりすると、「相続を承認した」とみなされ、放棄ができなくなります。
3.相続放棄後の影響
相続放棄をすると、その相続人は一切の財産や負債を引き継がなくなりますが、次順位の相続人に相続権が移るため、他の家族に負担がかかる可能性があります。
たとえば、故人の子が相続放棄をした場合、その次の相続人である兄弟姉妹や甥姪が相続をすることになります。
家族間のトラブルを避けるためにも、事前に話し合っておくことが重要です。
相続放棄をすると、故人の財産や負債を一切引き継がずに済みますが、代わりに他の相続人が負債を引き継ぐ可能性があるため、事前に家族と相談し、慎重に判断することが大切です。
また、財産と負債のバランスを確認し、相続の状況に応じて税理士などの専門家に相談し、適切な対策を取ることが望ましいでしょう。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。
最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。
しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。
だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。
灰江は正樹と佐賀美を引き合わせ、打ち解けた2人を見届けます。一方、記事の掲載を止められなかった羽毛田は、地鶏の関与を疑うのでした。そして、羽毛田は地鶏の陰謀を暴くため調査を進め、ついに大スクープを掴みます。
羽毛田は灰江に「ハイエナ、ワシと組まんか?」と提案。余命わずかな羽毛田は、ジャーナリストの誇りを懸け、司法の闇に挑む覚悟を決めます。敵同士だったハイエナとハゲタカが手を組み、巨悪との戦いがいよいよ始まるところで、物語は第9話へと続くのでした。
相続は、時に思いもよらぬ人間関係や秘密を明るみにすることがあります。遺産を巡る争いを防ぐためにも、生前の準備が不可欠です。特に、高齢化が進む現代では、遺言書の作成や財産管理を早めに検討することが重要です。相続で悩んだ際は、一人で抱え込まず、税理士などの専門家に相談し、円滑な相続のための対策を講じましょう。
相続は、家族の未来を大きく左右する重要な問題です。財産や負債の分配、遺産をめぐる意見の対立、法的な手続きの煩雑さなど、相続に関する課題は多岐にわたります。
特に、遺言書がない場合や、負債が残るケースでは、相続人同士の話し合いだけでは解決できない問題も多く、思わぬトラブルに発展することも少なくありません。
こうしたトラブルを防ぐためには、生前からの準備が不可欠です。遺言書の作成、家族会議の実施、相続税対策など、早めに計画を立てることで、スムーズな相続を実現することができます。
「相続は突然訪れるもの」と言われるように、準備をしないまま相続が発生すると、家族にとって大きな負担となります。相続が「争族」にならないようにするためにも、今からできることを考え、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中