相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。

一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

佐藤 智春

人生100年時代といわれる現代において、「終活」はもはや特別な行為ではなく、誰もが取り組むべき日常的な備えになりつつあります。近年では、スマートフォンやインターネットの普及により、「デジタル終活」という新たな分野にも注目が集まっています。東京都国分寺市のような都市部でも、2025年4月1日時点で65歳以上の高齢者は総人口の21.7%を占めており、高齢者の一人暮らし世帯も増加傾向にあります。こうした背景から、デジタル終活の重要性はますます高まっています。
私たちの暮らしに深く根付いたデジタル情報。今こそ、スマートフォンやパソコンに残る写真、SNSアカウント、ネット銀行や電子マネーなどの「デジタル資産」を整理し、遺された家族に混乱を与えないよう準備をしておくことが求められています。この記事では、「デジタル終活」とは何か、エンディングノートや遺言書との関係、そして実際の進め方や注意点について、わかりやすく解説します。
スマートフォンやインターネットが当たり前となった現代、私たちの生活には多くの「デジタル情報」が存在しています。写真や連絡先、銀行口座の情報からSNSの投稿に至るまで、日々の営みがデータとして蓄積されていく時代です。そんな中で注目されているのが「デジタル終活」です。

「デジタル終活」とは、自分の死後に残るデジタル情報を整理し、家族や相続人が困らないよう備える活動を指します。対象となる「デジタル遺品」は年々多様化しており、次のようなものが含まれます。
パソコン・スマホに保存された写真、動画、連絡先
SNSアカウント(Facebook、Instagram、Xなど)やメールアカウント
ネットバンキング、仮想通貨、ネット証券の取引履歴
サブスクリプション(Netflix、Amazon Primeなど)
クラウドストレージ(Googleドライブ、iCloudなど)
QR決済サービスやポイントサービス(〇〇Pay、楽天ポイントなど)
これらをそのまま放置しておくと、課金が継続されたり、個人情報が流出したり、重要な財産が見落とされたまま相続手続きが進んでしまったりと、家族に大きな負担がかかるリスクがあります。こうした背景から、デジタル終活の必要性が高まりつつあります。
東京都国分寺市は、都心へのアクセスと自然環境のバランスが取れた住みやすいエリアであり、地域に根ざした教育機関や図書館、地域包括支援センターといった「知的資源」も豊富です。こうした特性もあって、人生を主体的に締めくくるための「終活」への関心は高く、国分寺市役所ではエンディングノートを配布するなど、地域全体で終活を支援する取り組みも見られます。
自分の死後に何を残すのか、何を整理しておくべきかを考えることは、残された家族への「最後の思いやり」とも言えるでしょう。なお、デジタル情報の取り扱いや相続、アカウント管理などは専門性が高い分野も含みます。対応に不安がある場合は、相続の専門家などに相談することをおすすめします。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
「自分の意思をどのように家族に残すか」これは、デジタル終活を含む終末期の準備において、避けては通れない大切なテーマです。特に、デジタル資産やデジタル遺品の存在が一般化している現代では、「エンディングノート」と「遺言書」の活用が非常に有効とされています。
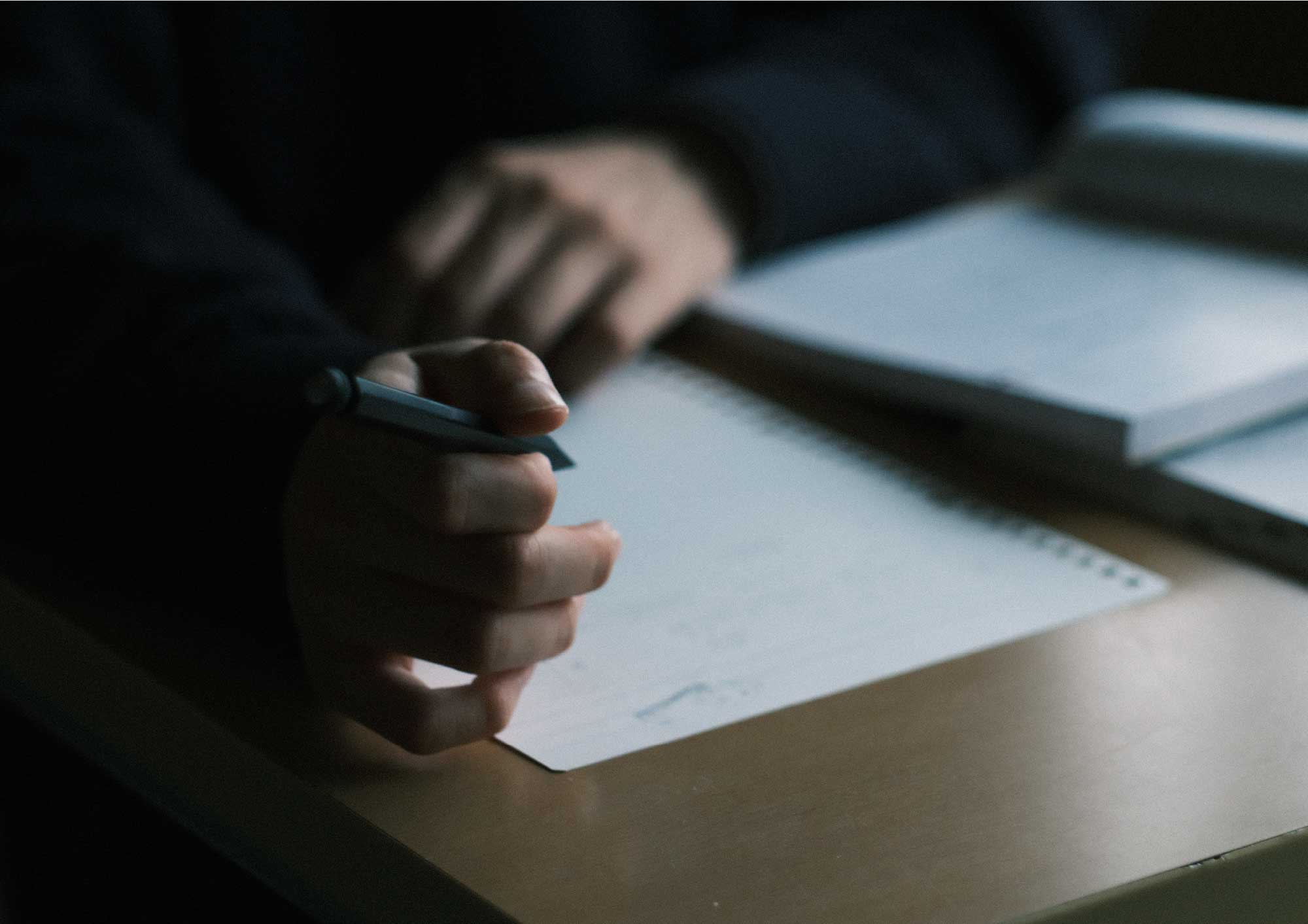
エンディングノートの役割とは?
エンディングノートは、法的な効力こそありませんが、自分の考えや希望を自由に記録できる「人生の備忘録」として広く活用されています。以下のような多岐にわたる情報を記すことができます。
基本情報(氏名・住所・連絡先)
医療・介護に関する希望(延命治療の可否など)
財産の概要(預金、不動産、保険契約など)
デジタル遺品の管理(ログイン情報や保管場所)
葬儀・お墓に関する希望
家族や知人へのメッセージ
国分寺のように高齢の親世代と離れて暮らす子世代が多い地域では、家族間での情報共有手段としても注目されています。ただし、エンディングノートには法的な拘束力がないため、財産の分配や正式な遺志を明確に残したい場合は、遺言書との併用が不可欠です。
遺言書とくに「公正証書遺言」の重要性
遺言書は、相続や財産分配について自分の意思を法的に示すための書面であり、法的効力を持つ重要な文書です。とりわけ、近年増えているデジタル資産(ネット証券や仮想通貨など)についても、遺言書に具体的な引き継ぎ先や方法を記しておくことで、相続人間のトラブルや情報の見落としを防ぐことができます。その中でも特におすすめしたいのが「公正証書遺言」です。公正証書遺言とは、公証人役場で2名の証人の立ち合いの元で作成し、公文書として成立する遺言の形式です。以下のような明確なメリットがあります。
法的に無効となるリスクが極めて低い
原本が公証役場に保管され、紛失・改ざんの心配がない
家庭裁判所の検認手続きが不要で、速やかに相続が可能
特にデジタル資産は発見が遅れることもあるため、遺言書の中で明記しておくことが、相続人にとっても大きな安心につながります。
エンディングノートで気持ちや考えを整理し、遺言書で法的な手当てをする。この二段構えが、家族や大切な人たちに「混乱」ではなく「感謝」を残すデジタル終活の鍵です。ただし、遺言書の作成やデジタル資産の取り扱いには専門的な知識が求められる場面も多くあります。不備や誤解があると、かえってトラブルの火種になることも。不安がある方は、税理士などの相続専門家に早めに相談することも大切です。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
デジタル終活の準備が不十分なまま亡くなると、残された家族がデジタル遺品の対応に追われるケースが増えています。スマートフォンやパソコン、ネットサービス上にある情報や契約は、物理的な遺品とは違って「見えにくく、気づきにくい」ため、トラブルに発展しやすいのが特徴です。ここでは、実際に多く見られるデジタル遺品整理のトラブルと、その事前対策をご紹介します。

パスワードが分からない
スマホやPCのロックが解除できず、遺族が金融情報や連絡先にアクセスできないケースが多く見られます。あらかじめ、信頼できる人にパスワードの保管場所や管理方法を伝えておくことが必要です。
相続財産の調査が進まない
ネットバンキングや証券取引、仮想通貨など、紙の通帳や証券が存在しない場合、何を所有していたかすらわからないまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。結果的に相続人の調査に時間がかかり、トラブルに発展することも。
思わぬ借金が発覚する
消費者金融の契約やクレジットカードのリボ払いなどが、スマホのアプリやオンライン契約で行われている場合、負債の存在が死後まで発覚しないことがあります。債務は相続の対象となるため、3か月以内の相続放棄や限定承認など、法的手続きのタイミングも重要です。
SNSアカウントが放置される
死後も公開状態のまま放置され、家族が削除に困るケースが増えています。アカウント情報や削除希望の有無をエンディングノート等に明記しておくと、家族の対応がスムーズになります。
会費・サブスクリプションの継続課金
解約手続きがなされず、費用が引き落とされ続けることも。契約状況の一覧を作成し、どこで何に登録しているかを家族が把握できるようにしておくと安心です。
デジタル遺品の問題は、放置すると家族間のトラブルや経済的損失、法的手続きの遅れにつながるリスクがあります。とくにネットバンキングや仮想通貨などは、扱いに専門知識が求められるため、一人で抱え込まず、専門家に相談することがとても重要です。弁護士・司法書士・行政書士などの専門家であれば、遺言書やエンディングノートの記載内容の相談に加え、デジタル資産の法的整理にも対応できます。国分寺市内にも、みらいえ相続グループなどの終活や相続に詳しい専門機関がありますので、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。
最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。
しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。
だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。
デジタル終活は、スマホやパソコンとともに暮らす現代人にとって、避けて通れない課題となりました。特に東京・国分寺のような都市部では、親と子が離れて暮らしているケースも多いため、エンディングノートや遺言書を活用した情報共有が大切です。「自分の死後、家族に迷惑をかけたくない」「大切な情報や想いをきちんと伝えたい」そんな気持ちから始まる終活の第一歩として、ぜひ「デジタル終活」についても意識してみてください。小さな備えが、大きな安心につながります。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中