相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。

一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

佐藤 智春

突然「余命宣告」を受けると、頭をよぎるのは「これからどう過ごすか」だけではありません。「残される家族に迷惑をかけたくない」「財産をきちんと渡したい」と考える方も多いでしょう。体調や気分がすぐれない中で、さまざまな手続きを進めるのは容易ではありません。
しかし、限られた時間の中でも、できる相続対策は数多くあります。財産の整理や遺言書の作成、相続税対策、さらには養子縁組なども含めた対策によって、家族の負担や将来のトラブルを大きく軽減することが可能です。
相続というと「まだ先の話」と捉えられがちですが、余命を告げられた今だからこそ、現実的に取り組むべき優先順位があります。本記事では、余命宣告後でも実行できる具体的な相続の備え方について、実務と制度の両面からわかりやすく解説します。この記事が、ご本人とご家族の安心に向けた一歩となることを願っています。
相続の第一歩は「財産の整理」です。どのような財産があり、どこにあるのか、誰が相続する可能性があるのか。それを明らかにすることが、相続トラブルの防止にもつながります。
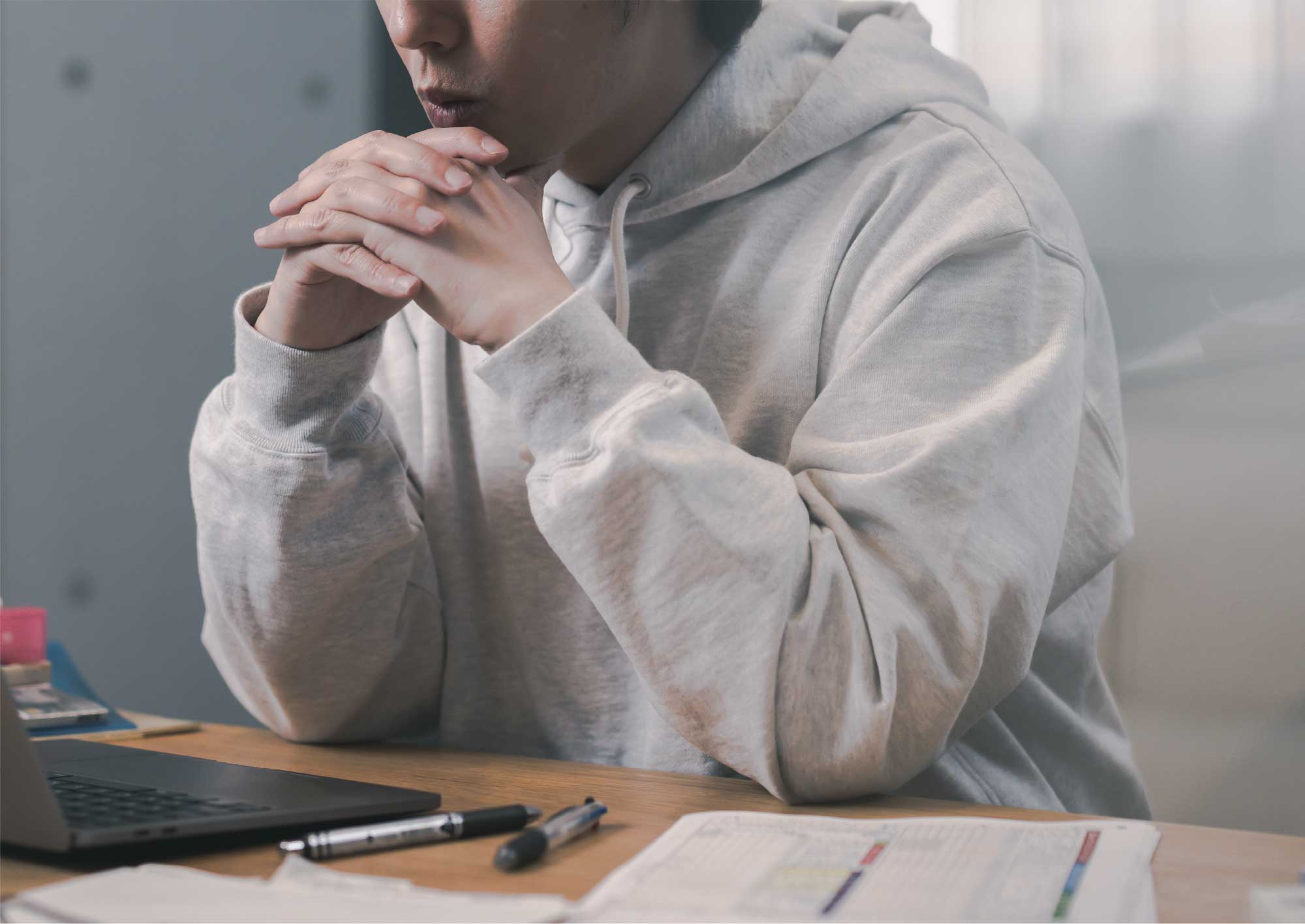
財産整理の基本項目
預貯金、株式、不動産などの資産一覧を作成
借金、未払い金などの負債も記録
共有名義の不動産がないか確認
ネット銀行や証券のID・パスワードを家族に伝える
実務面での整理ポイント
口座を1~2行程度に集約しておく
保険証券や契約書を一か所にまとめておく
相続税の納税資金が足りない場合は、一部資産を現金化
名義変更されていない土地・建物は名義整理を行う
非課税の財産
仏壇・墓地などの「祭祀財産」は相続税の対象外
大切なのは自身の財産を把握し「誰に、どのように引き継いでほしいか」という意思を明確にしておくことです。その意思表示こそが、遺されたご家族や大切な人たちを支える第一歩となります。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
財産の内容を整理できたら、次は「誰にどう残すか」を明確にするステップです。遺言書や生命保険の活用、非課税制度の利用など、限られた時間でも有効な対策はあります。

遺言書の作成
遺言書にはいくつかの種類がありますが、特によく利用されるのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。それぞれに特徴があるため、目的に応じた選択が大切です。
自筆証書遺言
遺言者が全文を自筆し、日付・署名・押印をして作成する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できますが、形式の不備による無効リスクや、紛失・改ざんの恐れがあります。相続時には家庭裁判所の「検認」も必要です。
公正証書遺言
公証人が関与して作成される遺言書で、原本は公証役場に保管されます。形式不備や紛失の心配がなく、検認手続きも不要です。費用や証人が必要になりますが、公文書として強力な効力を持つため、内容を確実に実現したい方には最も安全な方法です。
エンディングノートは遺言書としての効力がないため注意しましょう。
以下のようなケースでは、公正証書遺言を強くおすすめします。
家族関係が複雑である
相続人に認知症の方がいる
行方不明者が相続人である
特定の人に多く残したい、または渡したくない希望がある
相続人以外(パートナー、友人、団体など)に遺贈したい
2023年度には全国で6,948件の相続財産管理人が選任されています。つまり、相続人がいない、または遺言がないという理由で、財産が第三者の管理下に置かれた件数がそれだけあるのです。
相続税対策としての工夫
相続税を軽減するためには、制度を上手に活用することが大切です。代表的な対策をご紹介します。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続する財産は、1億6,000万円または法定相続分まで非課税になります。
教育資金・住宅資金の贈与
子や孫への教育資金や住宅資金を一括で贈与する場合、一定の要件を満たせば非課税となる特例があります。
非課税財産の購入
墓地や仏壇などの非課税財産を生前に購入しておくことも、有効な対策になります。
養子縁組による基礎控除の拡大
控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
節税目的のみの養子縁組は否認される可能性があり、追徴課税のリスクもあります。
法的・税務的な判断が必要なため、必ず相続税に詳しい税理士にご相談ください。
また、相続人がいない場合でも「遺贈寄付」という手段で、信頼する団体やNPO法人に財産を託すこともできます。遺言で意思を示しておけば、国庫に帰属せず、社会に活かす形で「想い」を未来へ届けられます。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
相続対策を進める中で、見落としがちな注意点やリスクについても知っておくことが大切です。

遺言と遺留分
配偶者や子には遺留分があり、すべての財産を特定の人に相続させるとトラブルになる可能性があります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
二次相続に注意
一次相続で非課税でも、配偶者の死後に発生する二次相続では相続税が重くなることがあります。
安易な資金移動に注意
死亡前の預金引き出しや贈与は、課税対象になることがあるため、理由や記録を明確にしておくことが大切です。
遺言を残さなかったことで、故人の意思が反映されず、家族が困ってしまうケースは少なくありません。「自分にはまだ早い」「うちはもめない」と思っていても、いざ相続が発生すると、手続きや話し合いに多くの時間と労力がかかることがあります。
家族に迷惑をかけたくないとお考えであれば、元気なうちに意思を明確にし、相続対策を始めることが大切です。そのためには正確な知識と判断が必要ですので、相続に詳しい税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。
最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。
しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。
だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。
余命宣告という厳しい現実の中で、それでも「家族に何かを遺したい」「迷惑をかけたくない」と願うのは、かけがえのない想いです。限られた時間の中で行う相続対策は、心身ともに負担が大きく、すべてを一人で抱えるのは困難です。たとえ家族がいなくても、遺贈寄付などを通じて「生きた証」を未来へとつなぐことができます。
だからこそ、税理士や司法書士などの専門家に頼り、実務の整理から法的サポートまでを一緒に行っていくことが、最も現実的で効果的な方法です。みらいえ相続グループでは、相続専門のスタッフが一人ひとりの状況に応じて、最適なアドバイスをご提供しています。まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。あなたの不安に、私たちが寄り添います。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中