相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。

一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

佐藤 智春

相続税は累進課税方式で、相続財産の総額に応じて税率が変わります。また、基礎控除や負債の控除が適用されるため、高額な財産を相続しても必ずしも課税されるとは限りません。
しかし、都市部では土地の評価額が高く、1億円以上の資産を相続するケースも珍しくありません。そのため、相続税がどのくらい発生するのか、事前に把握しておくことが大切です。
本記事では、1億円の遺産にかかる相続税を例にし、高額資産をお持ちの方へ税負担を軽減する控除や特例の活用法についてもご紹介します。
相続税の金額は、相続財産の総額だけでなく、法定相続人の数や適用できる控除・特例によって大きく変わります。例えば、法定相続人が多い場合や、配偶者控除・小規模宅地等の特例を活用できる場合、1億円の遺産があっても相続税がゼロになるケースもあります。
一方で、法定相続人が1人で特例を利用できない場合、1,220万円の相続税が発生する可能性があります。相続税の概算を把握するには、「相続税の速算表」を活用するのが便利です。

富裕層の相続には慎重な対応が必要
相続は多くの人に関わる問題ですが、特に高額な資産をお持ちの方は、慎重な対応が求められます。前述のとおり、相続税は累進課税方式のため、財産の規模が大きくなるほど税負担が増し、手続きも複雑になりがちです。
相続税の計算や資産の評価、遺産分割の方法を誤ると、思わぬ負担が発生することもあります。ここからは、富裕層の相続が大変な理由とその背景について詳しく見ていきましょう。
累進課税制度とは?
富裕層の相続税が一般の方よりも高くなるのは、累進課税制度によるものです。相続税は、財産が多いほど税率が上がり、最高で55%に達します。一般的には、相続財産が基礎控除の範囲内に収まることが多いため、税負担が発生しないケースもあります。
しかし、富裕層は不動産、株式、事業資産など高額な財産を多く所有しているため、課税対象となる金額が大きくなります。
富裕層の相続手続きが複雑な理由
富裕層の相続手続きが複雑になるのは、資産の種類が多岐にわたり、相続税の負担が大きいためです。
1.資産の評価が難しい
不動産、株式、事業資産、美術品などは市場価格が変動しやすく、適正な評価を行う必要があります。
2.遺産分割の調整が必要
相続人が多い場合や、事業承継が絡むと、遺産分割の協議が長期化しやすくなります。
3.税負担への対策が求められる
高額な財産に対する相続税率が高いため、節税対策や納税資金の確保が欠かせません。
このように、富裕層の相続には多くの課題が伴います。しかし、適切な対策を講じることで、税負担を抑え、円滑に相続を進めることが可能です。特に、相続税の申告や資産の評価、遺産分割の調整などは専門的な知識が求められるため、専門家のサポートを活用することが重要です。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
高額な資産をお持ちの方は、控除や特例を活用することで相続税の負担を軽減できます。適切な対策を講じることで、税額を抑えながら円滑な資産承継が可能です。
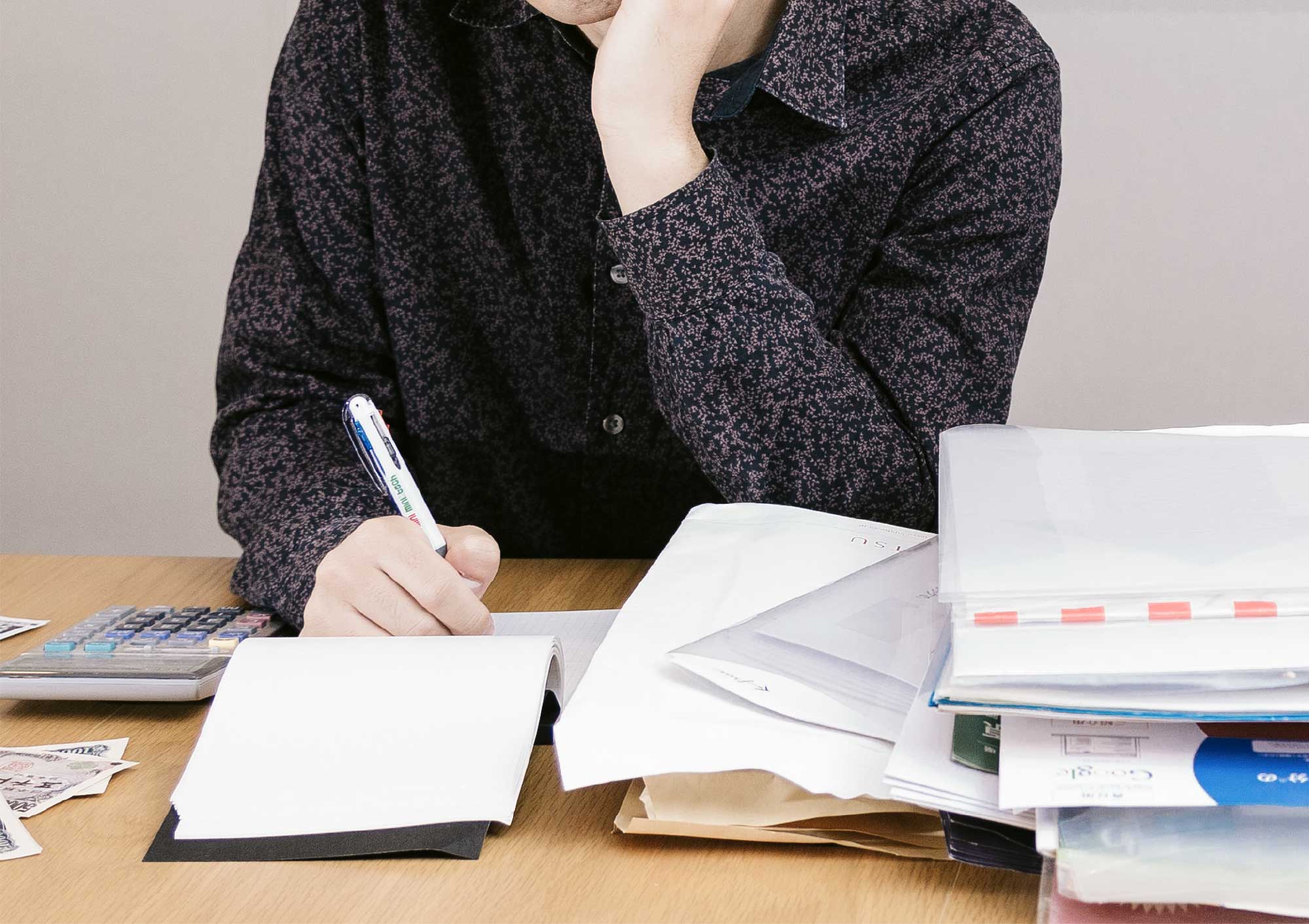
以下に、主な控除や特例をご紹介します。
1.配偶者控除(相続税の軽減)
配偶者が相続する場合、最大1億6,000万円または法定相続分まで非課税となり、税負担を大幅に軽減できますが、二次相続の負担も考慮が必要です。
2.小規模宅地等の特例(不動産の評価額軽減)
一定の要件を満たせば、自宅や事業用地の相続税評価額を最大80%減額でき、被相続人と同居していた配偶者や親族が継続居住する場合に適用されやすい制度です。
3.生命保険の活用(非課税枠の利用)
生命保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税となり、課税対象財産を減らせるうえ、納税資金の確保にも有効な手段です。
4.生前贈与(相続税の対象資産を減らす)
生前に贈与を行うことで相続財産を減らし税負担を軽減でき、年間110万円の非課税贈与や2,500万円までの相続時精算課税制度などの特例を活用できます。
5.事業承継税制(中小企業の経営者向け)
一定の要件を満たせば会社の株式にかかる相続税・贈与税が100%猶予または免除され、後継者が代表権を引き継ぐことが適用の条件となります。
6.不動産の有効活用(評価額の引き下げ)
資産を現金ではなく不動産として所有すると相続税評価額が低くなることが多く、賃貸物件の活用で評価額を抑え、争族対策にも役立ちます。
7.遺言書の活用(遺産分割トラブルの回避)
遺言書を作成することで資産の分割方法が明確になり、相続トラブルを防げるうえ、遺産分割協議が不要となり、税負担を考慮した承継もスムーズに進められます。
高額な資産をお持ちの方は、相続税の負担が大きくなりやすいため、控除や特例を適切に活用することが不可欠です。特に、配偶者控除、小規模宅地等の特例、生命保険の非課税枠などは基本的な節税対策として有効であり、さらに生前贈与や不動産活用、事業承継税制を組み合わせることで、より大きな節税効果が期待できます。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
高額資産の相続は、通常の相続に比べて税負担が大きく、財産の評価や分割が複雑になりやすいため、慎重な準備が必要です。相続税の申告・納税はもちろん、納税資金の確保や遺産分割の方法によっては、後々トラブルが発生する可能性もあります。スムーズな相続を実現するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

1.相続税の負担を把握する
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、超えると課税対象です。申告・納税は10か月以内に行い、延滞すると加算税が発生します。高額資産は現金以外が多いため、納税資金の確保が重要で、物納や延納の選択肢も検討しましょう。
2.相続財産の評価と分割
不動産の評価方法には「路線価方式」「固定資産税評価額」「時価」などがあり、相続税額に影響します。自営業や会社経営者は、事業承継対策や税制の活用を検討が必要です。遺産分割協議がまとまらないと相続税申告に影響するため、遺言書や生前贈与を活用し、事前に分割方法を決めましょう。
3.節税対策
相続税を軽減するには、生前贈与の活用が有効です。暦年贈与は年間110万円まで非課税、相続時精算課税制度なら2,500万円まで非課税となります。配偶者控除を使えば最大1億6,000万円まで非課税になり、小規模宅地等の特例を適用すると、土地の評価額が最大80%減額されます。
4.相続トラブルの回避
相続トラブルを防ぐには、公正証書遺言の作成が有効です。生前に家族と話し合い、相続に関する認識を共有することも重要です。さらに、税理士・司法書士などの専門家に相談し、適切な対策を進めることで、スムーズな手続きを実現できます。
5.海外資産や特殊資産の注意点
日本の相続税は全世界の資産が対象となるため、海外不動産や預金も申告が必要です。申告漏れを防ぐため、資産を適切に把握しましょう。また、仮想通貨や未上場株式など評価が難しい資産は、相続時の価値算定方法を事前に確認し、適切な対応を準備することが重要です。
6.相続放棄や限定承認の活用
相続財産に負債がある場合、相続放棄や限定承認でリスクを回避できます。相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ申請すれば負債を引き継ぎません。限定承認は、相続財産の範囲内でのみ負債を相続する制度で、プラスの財産がある場合に有効です。状況を踏まえ慎重に判断しましょう。
高額資産の相続は、税金・分割・トラブル防止の観点から早めの対策が重要です。遺言書の作成や専門家の活用、生前贈与などを適切に組み合わせることで、円滑な相続を実現できます。将来の円満な相続のために、計画的な準備を進めていきましょう。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。
最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。
しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。
だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。
相続税の計算や控除・特例の適用は複雑で、高額資産をお持ちの方ほど慎重な対応が求められます。自己判断で手続きを進めると、申告漏れや評価ミスにより想定以上の税負担が発生することもあります。特に、遺産分割や納税資金の確保を誤ると、後々のトラブルにつながりかねません。
相続を円滑に進め、税負担を最小限に抑えるためには、相続専門の税理士に相談することが不可欠です。専門家のサポートを受けることで、正確な申告と適切な節税対策が可能となり、将来のリスクを回避できます。
相続は事前の準備が重要です。信頼できる専門家と連携し、円満な資産承継を実現しましょう。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中