相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。

一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

佐藤 智春
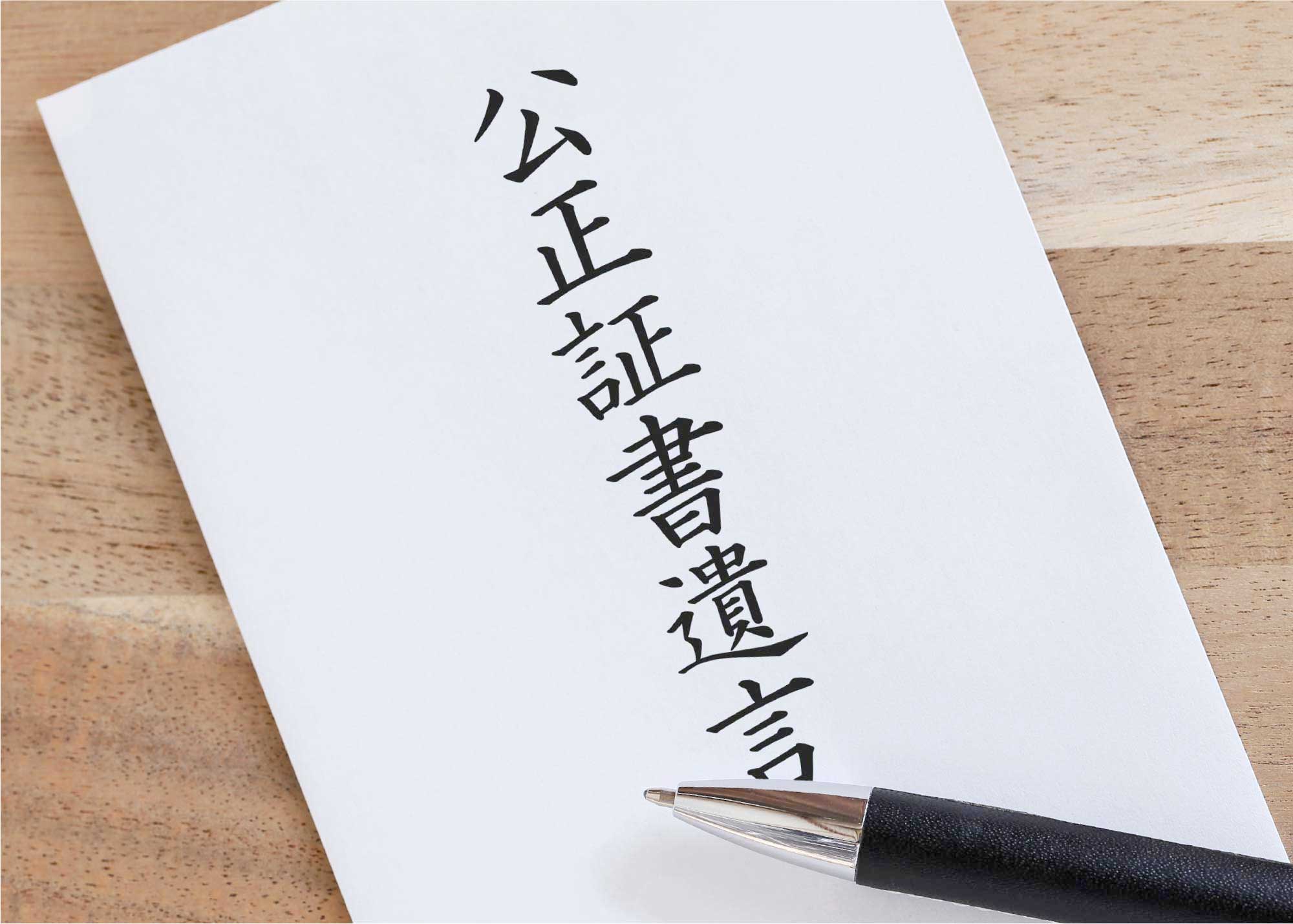
これまで「終活」は、高齢者が行うものと考えられてきました。しかし今、20代・30代の若者の間にも、「自分の人生を整理し、家族に迷惑をかけない準備をする」という考え方が広がりつつあります。
芸能人や著名人がメディアで終活について発信する機会も増えています。アーティストのちゃんみなさん(27)は、「13歳のころから遺書を書いています」と語り、死を意識することで「どう生きたいか」を見つめてきたといいます。また、タレントの田村淳さんも「遺書を書いたら人生のモチベーションが上がった」と語り、元気なうちに最期を考えることの大切さを伝えています。このように、終活は今、誰もが自分らしい生き方を選び取るための行動として注目されています。
一方で、高齢化の進行により相続が急増し、「家族の資産をどのように引き継ぐか」という問題が社会的な課題となっています。さらに、2025年10月からは、公証役場に行かなくても作成できる「デジタル公正証書遺言制度」が始まりました。これにより、オンライン上で法的に有効な遺言を作成できるようになり、終活や生前対策はこれまで以上に身近で実践的なものとなっています。本記事では、大相続時代の到来と社会の変化、終活と相続の基礎知識、生前対策とデジタル遺言制度など、現代の終活をわかりやすく解説していきます。
出典元|ちゃんみな「13歳のころから遺書を書いてます」
出典元|田村淳「元気な時こそ遺書を書く」
出典元|日本公証人連合会「公正証書の作成手続がデジタル化」
いま、日本は「大相続時代」と呼ばれる大きな転換期を迎えています。高齢化とともに相続が急増し、誰にとっても相続は身近な問題となりつつあります。総務省の人口動態統計によると、日本では年間およそ150万人が亡くなっており、その数は今も増加傾向にあります。
また、国税庁の発表によれば、相続税の申告件数は年間15万件前後に達しており、10年前と比べて大きく増加しています。もはや「相続」は特別な人だけの話ではなく、私たちの生活と密接に結びついた社会現象となっています。
出典元|厚生労働省「令和5年人口動態統計の概況」
出典元|国税庁「令和5年分相続税の申告事績の概要」

大相続時代とは
団塊の世代(1947〜1949年生まれ)が後期高齢者(75歳以上)となる2025年以降、相続件数が急増し、莫大な資産が世代間で移転する時代を指します。この現象は、医療・介護・社会保障・不動産市場など、社会のあらゆる領域に波及するといわれています。
特に「2025年問題」と呼ばれる社会課題と密接に関係しており、団塊世代約800万人が一斉に後期高齢者となることで、医療・介護費の増大、労働力人口の減少、そして相続の発生件数が同時に急上昇するという構図が生まれています。
大相続時代を生み出す要因
高齢化と長寿化の進行
日本人の平均寿命は女性87歳・男性81歳を超え、世界でも最長クラスです。その結果、「60代・70代の子が、90代の親から相続を受ける」という「高齢者どうしの相続」も増加しています。
出典元|厚生労働省「令和5年簡易生命表の概況」
相続税の課税強化
2015年の税制改正により、相続税の基礎控除額が「5,000万円+(1,000万円×法定相続人)」から「3,000万円+(600万円×法定相続人)」へ引き下げられました。これにより課税対象者は大幅に増加し、「普通の家庭」でも相続税の申告が必要なケースが珍しくなくなりました。相続税の申告件数は、ここ数年で増加し続けています。
出典元|国税庁「相続税改正-遺産に係る基礎控除額の引き下げ」
資産構造の多様化
かつての相続財産の中心は不動産と預貯金でしたが、現在は株式・投資信託・保険・退職金・暗号資産・クラウドファンディングなど多岐にわたります。これにより、調査・評価・分割・申告といった手続きは、かつてよりも格段に複雑化しました。
大相続時代がもたらす課題
空き家問題の深刻化
相続によって取得した不動産を活用せず放置されるケースが増えており、空き家問題が深刻化しています。総務省によると、2023年時点で全国の空き家総数は約900万戸、住宅総数に占める割合(空き家率)は13.8%に達しました。国土交通省も、空き家数が20年間で約1.5倍になったと報告しています。不動産や家財を次世代に残さず自分の代で整理する、いわゆる家じまいも注目されています。
出典元|総務省「令和5年住宅・土地統計調査」
出典元|国土交通省「空き家政策の現状と課題及び検討の方向性」
資産集中と経済影響
日本では、個人の金融資産が世代間で大きく偏って保有されている状況が明らかになっています。内閣府の報告によると、世帯主が60歳以上の世帯が保有する金融資産の割合は、令和元年時点でおよそ63.5%に達しています。また、金融資産の分布を年代別にみると、60歳代以上の保有割合が長期にわたり増加傾向にあるという報告もあります。
出典元|内閣府「令和6年版 高齢社会白書 – 就業・所得」
出典元|内閣府「第28回 税制調査会資料 – 世代別金融資産保有状況」
相続は、もはや一部の富裕層だけの問題ではなく、すべての家庭に関わる重要な課題です。相続を争いではなく、思いやりの継承にするためには、早めの準備と正しい知識が欠かせません。まだ先の話と考えず、自分の意思や考えを行動で示せるうちに、相続の専門家のアドバイスに耳を傾けながら、着実に対策を進めていくことが大切です。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
「終活」は、現代の若い世代にとって「自分らしい生き方を整える」という前向きな意味で捉えられています。エンディングノートの作成やデジタル資産の整理など、終活は死の準備ではなく、これからの人生をよりよく生きるための行動へと変化しました。
こうした生き方の整理は、やがて訪れる相続への備えにもつながります。終活の延長には、大切な財産を誰にどのように託すかという想いの整理も含まれます。ここでは、その土台となる相続の基本的な仕組みを見ていきましょう。

相続の基礎知識
相続とは
「相続」とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を、家族などの相続人が引き継ぐことをいいます。人が亡くなった時点で相続は発生し、誰が何をどれだけ引き継ぐのかは民法(相続法)によって定められています。
民法第882条(相続の開始)
人の死亡によって相続が開始する。
民法第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
相続の主な種類
法定相続
民法で定められた範囲と割合に従って、財産を引き継ぎます。相続できるのは、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など、法律で定められた「法定相続人」です。
遺言相続
遺言書によって、本人の意思に沿って財産を分けます。遺言書がある場合はその内容が優先され、ない場合は民法に基づき、相続人同士で話し合う「遺産分割協議」が行われます。
相続人とその順位
亡くなった人の配偶者は、常に相続人となります。血族の相続順位は次のとおりです。
第1順位:子(すでに亡くなっている場合は孫などの直系卑属)
第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
上位の相続人がいない場合に、次の順位の人が相続人になります。
相続財産の概要
相続財産には、現金・預貯金・不動産・株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。また、死亡保険金や死亡退職金など、死亡をきっかけに受け取る「みなし相続財産」も存在します。
相続は一生に何度も経験するものではありませんが、誰にでも訪れる可能性があります。家族に迷惑をかけないためにも、基本的なルールを知り、早めに準備しておくことが大切です。
また、相続には法的に複雑なルールや手続きが多く、相続税の申告には専門的な知識が必要です。控除や特例など、状況に応じて活用できる制度も多岐にわたります。相続の専門家に相談し、正しい知識とサポートを得ながら進めていくことをおすすめします。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
「生前対策」というと、節税や財産分与の準備を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、本来の目的は 自分の想いを確実に形にし、家族の負担を減らすこと にあります。財産をどう分けるかだけでなく、「誰に何をどのように伝えるのか」という意思を整理することこそが、生前対策の第一歩です。代表的な生前対策としては、次のようなものがあります。

生前対策の一例
遺言書の作成
遺言書は、自分の意思を明確に残すための最も確実な手段のひとつです。形式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。なかでも、公証人が関与して作成する「公正証書遺言」は、法的効力が高く、形式の不備によって無効となるリスクがほとんどありません。相続人同士の争いを防ぎ、自分の意思を確実に反映させるための、最も安心できる方法といえます。
生前贈与の活用
生前贈与は、相続財産をあらかじめ整理し、将来の争いと相続税を減らす有効な方法です。年間110万円までの贈与には「基礎控除」が適用され、税負担を抑えることができます。また、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産の贈与に対して最大2,000万円までの非課税特例を利用することも可能です。
出典元|国税庁「贈与税のしくみ」
出典元|国税庁「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
家族信託・任意後見制度
将来、判断能力が低下した場合に備えるには、「家族信託」や「任意後見制度」の活用が効果的です。家族信託では、信頼できる家族に財産管理を任せ、本人の意思に沿った資産運用を続けることができます。また、任意後見制度を併用すれば、判断力が衰えた後でも生活費の管理や契約行為を円滑に進める体制を整えることができます。
生命保険の活用
生命保険の死亡保険金は、相続発生直後に現金として受け取れるため、納税資金や葬儀費用の確保に役立ちます。保険金は「受取人固有の財産」として扱われ、遺産分割協議の対象外になる点も大きな利点です。
財産目録とデジタル資産の整理
自分の財産を一覧にまとめておくことで、家族が手続きをスムーズに進められるようになります。預貯金や不動産だけでなく、ネットバンクや電子マネー、サブスクリプション契約などのデジタル資産も忘れずに整理することが大切です。財産情報を「見える化」しておくことは、家族への安心と円滑な相続につながります。
公正証書遺言のオンライン化
これまで公正証書遺言を作成するには、公証役場へ直接出向き、公証人と対面で手続きを行う必要がありました。しかし、2025年10月1日施行の改正公証人法(令和5年法律第53号)により、公正証書のデジタル化が始まりました。これにより、遺言の作成方法が大きく変わります。
公正証書の電子化が導入
従来は紙で作成・保管されていた原本が、電子データ(PDF)として作成・保存されるようになり、正本・謄本も電子ファイルで発行可能になります。火災や紛失のリスクが減り、管理の負担も軽くなります。
リモート方式の導入
WEBシステムを利用し、公証人と画面越しに面談しながら署名を行う仕組みにより、オンラインで遺言を作成できるようになりました。これにより、高齢者や遠方在住の方でも、自宅から安心して遺言書を作成できます。
出典元|日本公証人連合会「公正証書の作成手続がデジタル化」
遺言書作成の基本
遺言書とは、亡くなった方(被相続人)が「誰に、どの財産をどのように渡したいか」を明確に示す法的な文書です。相続をめぐるトラブルを防ぎ、自分の意思を確実に実現するための重要な手段といえます。遺言書の形式は、主に次の2種類があります。
自筆証書遺言
本人が全文を自筆で書き、署名・押印する方式です。ただし、内容や形式に不備があると無効になるおそれがあり、法律の要件を満たしていないケースも少なくありません。また、専門家の確認を経ずに作成された遺言書は、相続人間での解釈の違いや争いの原因になることもあります。費用はかかりませんが、法的な確実性という点では注意が必要です。
公正証書遺言
公証人が本人の意思を確認し、公証役場で正式な文書として作成・保管する方式です。法的効力が高く、形式の不備によって無効になることがほとんどありません。また、家庭裁判所での検認も不要で、相続開始後も速やかに手続きを進められます。
みらいえ相続グループでは、最も確実に本人の意思を残せる方法として、公正証書遺言の作成を推奨しています。専門家が関与することで、誤りや不利益を防ぎ、家族にとって最も安心できる遺言を整えることができます。
作成時の注意点
遺言書を作成する際には、民法で定められた「遺留分」にも注意が必要です。遺留分とは、配偶者や子など一部の相続人に保障される最低限の相続分のことで、たとえ遺言があっても、その範囲を侵害することはできません。なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
公正証書遺言のオンライン化は、遺言をより身近で効率的なものに変える大きな一歩です。手続きが簡単になった一方で、法的要件や税務上の判断には専門知識が欠かせません。形式の不備で無効になったり、税負担の想定が誤っていたりすると、せっかくの想いが正しく伝わらないこともあります。
みらいえ相続グループでは、税理士・行政書士・不動産の専門家が連携し、お客様の想いと状況に合わせた最適な遺言書づくりをサポートしています。「遺す方」と「遺される方」双方が安心できるよう、相続税対策や二次相続まで見据えた提案を行います。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。
最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。
しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。
だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。
公正証書の作成手続きがデジタル化され、公証制度は大きく進化しました。原本は紙から電子データへ移行し、正本・謄本の交付方法も柔軟に。さらに、要件を満たせばリモート方式による作成も可能となり、これまで公証役場に行くのが難しかった方にとっても、遺言がより身近なものになります。一方で、本人確認や意思確認の重要性は一層高まり、全てのケースでオンライン対応ができるわけではありません。制度を正しく理解し、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
みらいえ相続グループでは、税理士・行政書士・不動産の専門家が連携し、公正証書遺言の作成から相続税対策、生前贈与、登記までをトータルでサポートしています。相続は「人生の終わり」ではなく「家族の未来」を築くプロセスです。生前対策や遺言作成が少しでも気になる方は、ぜひ一度、みらいえ相続グループへご相談ください。専門家があなたの状況に合わせた最適な方法を丁寧にご提案いたします。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中