相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。

一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

佐藤 智春
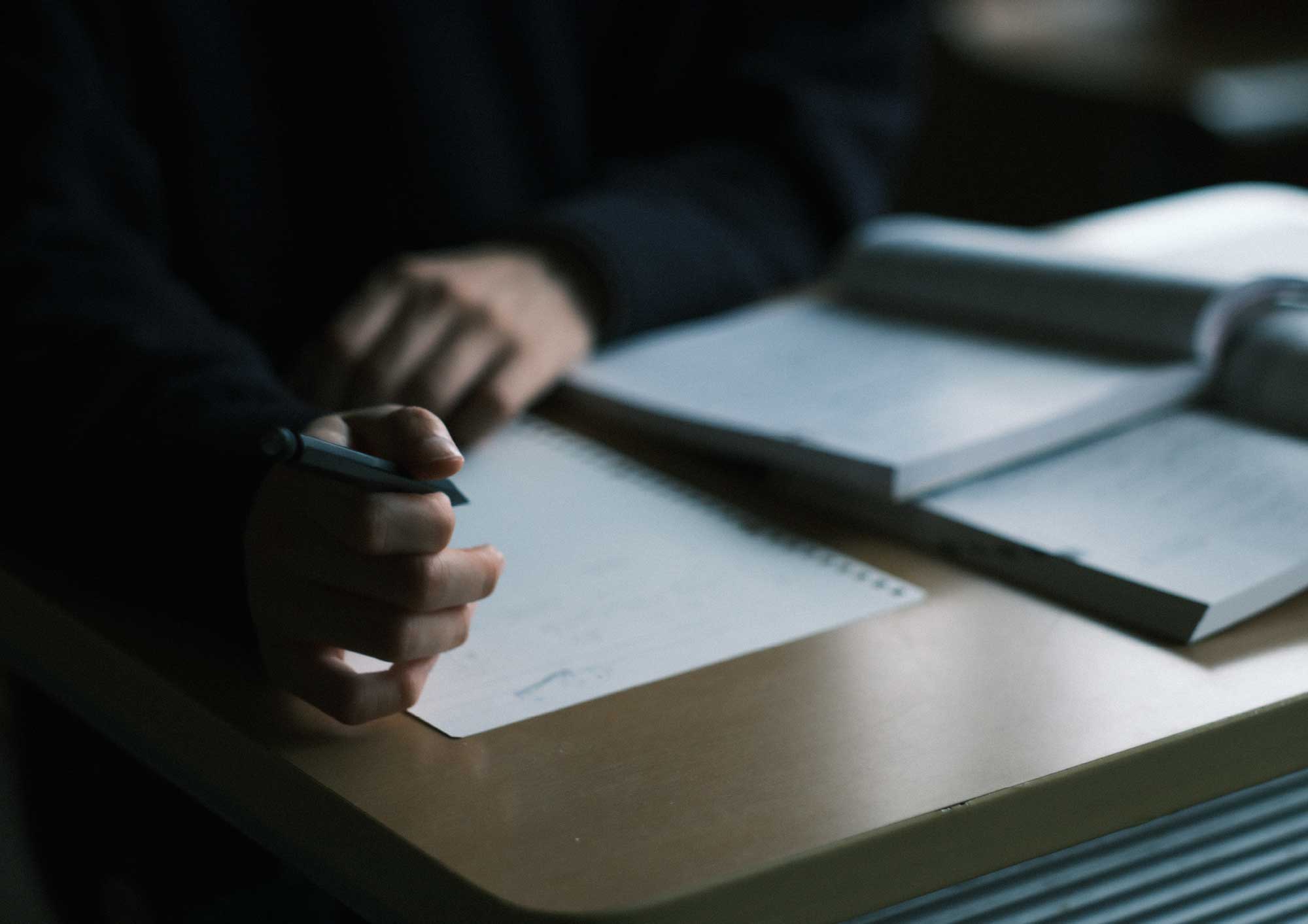
遺産相続ドラマ「相続探偵」第9話が放送されました。物語はいよいよクライマックスへ。主人公・灰江七生(ハイエナ)は、育ての父の名誉を回復するため、因縁の相手である地鶏健吾との対決に踏み出します。
今回は、3つの遺言書が物語を大きく動かす鍵となります。ドラマの展開を追いながら、言書の意味と役割といった相続にまつわる重要なテーマを専門家の視点で解説していきます。
18年前、和宏のバス事故は突風によるものでしたが、居眠り運転と報道されて汚名を着せられました。裏で糸を引いていたのは、灰江の実の父で法曹界の重鎮・地鶏健吾。灰江は父の無念を晴らすため、記者・羽毛田と手を組み、真実を追い始めます。
地鶏や政界のドン・浅葉が関与する権力の闇、浅葉の孫・台矢の薬物事件のもみ消し、そしてSNSでの告発。やがて世論が動き始め、灰江は国家賠償請求に向けて動き出します。一方、令子は真実を語らせるために、元裁判官・煤田に命がけの説得を試みます。また羽毛田は、真相を託す遺言書を残し、何者かに襲撃されてしまうのでした。
第9話の序盤、灰江は、亡き父・和宏が起こしたバス事故の再検証に乗り出します。事故は突風による不可抗力だったものの、居眠り運転との報道により世論が加熱。裁判でも過失が認定され、父の名誉は傷つけられてしまいました。
背後で裁判に圧力をかけていたのは、灰江の実父で法曹界の重鎮・地鶏健吾。真実を明らかにするため、灰江は国家賠償請求という大きな一手を打つ覚悟を固めます。正義と権力の対決が、ここに始まります。
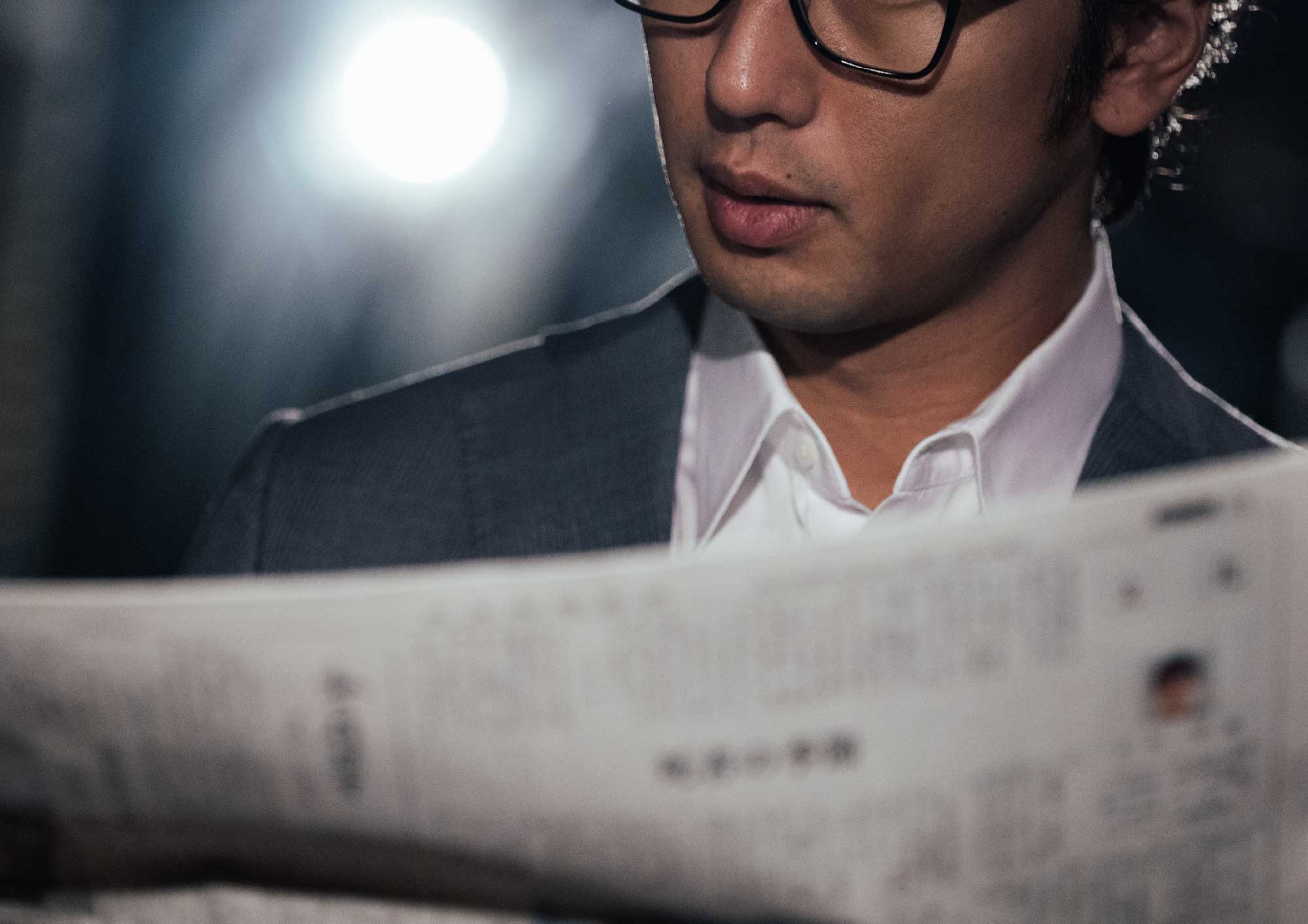
視聴者の疑問「相続で揉めるのはどんな時?どうすれば避けられるの?」
専門家の回答「事前の対策と冷静な話し合いが、争いを防ぐカギです。」
ドラマでは、主人公・灰江が父の汚名を晴らすために国家賠償請求を目指し、強大な権力者と対峙します。中には、脅しや告発、過激な手段に出る場面もありました。
現実の相続では、そこまで激しい対立には至らなくても「遺産の分け方」「相続人の認識違い」「話し合いの不足」などがきっかけでトラブルに発展することが少なくありません。こうした争族を避けるためには、以下のような生前対策が重要です。
1.遺言書の作成
遺産の分け方を明確にする最も基本的な方法です。法的に有効な形式(特に公正証書遺言)で作成すれば、相続人間の認識違いや争いを防ぐ効果があります。
2.家族会議の実施
あらかじめ相続について家族で話し合う機会を持つことで、認識のズレや不安を解消できます。特に不動産や事業承継が絡む場合は、事前に役割や方針を共有することがトラブル防止に効果的です。
3.財産内容の整理
財産の全体像(不動産・預貯金・保険・債務など)を一覧化しておくことで、相続時の混乱を避けられます。相続人が財産の存在を把握していないと、無用な疑念や対立を招く原因になります。
4.生前贈与の活用
相続が発生する前に、一部の財産を計画的に贈与しておく方法です。特に、年間110万円の非課税枠や住宅取得・教育資金の特例などを活用すれば、節税効果とトラブル回避の両面でメリットがあります。
5.家族信託の導入
認知症や意思判断能力の低下に備え、信頼できる家族に財産管理を託す仕組みです。資産凍結リスクの回避や、相続時の意向の実現などに役立ちます。柔軟な対応ができるのが特徴です。
相続は、家族のつながりが問われる大切な場面でもあります。将来の争いを防ぐためにも、早めに準備を始め、必要に応じて専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
第9話の中盤、国家賠償請求を進めるためには、かつての裁判を担当した元裁判官・煤田の証言が不可欠だと知った令子は、彼の自宅を訪ねます。証言を拒み続ける煤田に対し、令子は自ら書いた遺言書を差し出し「あなたが証言しないなら、私はここで命を絶ちます」と強い覚悟で迫ります。
ドラマは衝撃的な展開を迎えますが、その行動の裏には、灰江とその家族の無念を晴らしたいという深い想いがありました。
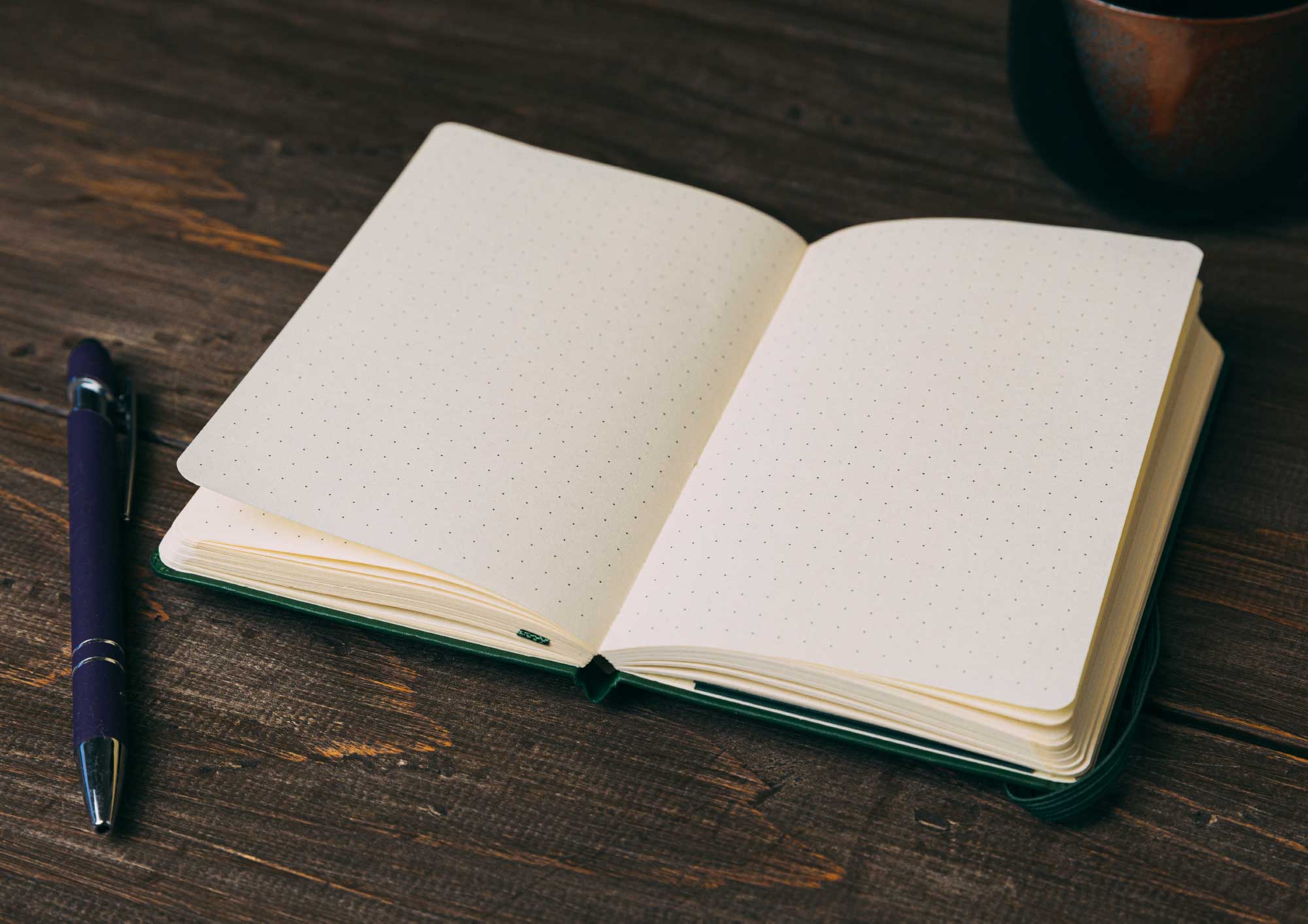
視聴者の疑問「遺言書って、好きに書いてもいいの?効力は?」
専門家の回答「正しい形式と意図で、遺言書を考えましょう。」
ドラマでは、令子が元裁判官・煤田に証言を迫るため、自らの遺言書を使って命がけの覚悟を見せる場面が登場します。ドラマならではの演出ですが、本来の遺言書の目的は「自分の想いを正しく、法的に遺すこと」です。そのためには、その種類や形式を正しく理解しておく必要があります。
代表的な遺言書の種類
遺言書は3種類あり、作成方法や安全性、費用などが異なります。選ぶ形式によって、相続トラブルを防ぎ、家族に安心を残すことができます。
1.公正証書遺言(おすすめ)
公証役場で作成する、最も安全かつ確実な遺言書。検認不要で、法的トラブルも少ないのが特徴です。
2.自筆証書遺言
費用をかけずに自分で作れるが、形式不備や内容の曖昧さで無効になるケースもあります。法務局で保管制度を利用することも可能です。
3.秘密証書遺言
内容を他人に知られずに作成できるが、現在ではあまり使われていません。
法的な遺言書の形式
遺言書は民法で定められた形式を守らなければ、無効となる可能性があります。形式不備による無効は実際に多く、特に注意が必要です。
1.公正証書遺言の場合
遺言者が内容を口述し、公証人が文書にまとめて作成する遺言書で、公証役場に原本が保管され、検認が不要で最も確実性が高く、法的トラブルを防ぎたい方に適した方式です。
2.自筆証書遺言の場合
自分で全文を手書きして作成する遺言書で、費用がかからず手軽ですが、日付・氏名・押印など形式の不備があると無効になる可能性があり、原則として家庭裁判所での検認も必要です。
3.秘密証書遺言の場合
遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と証人の前で封印した書面を提出する方式で、内容は誰にも知られませんが、形式に不備があっても気づかれにくく無効になるリスクが高いため、現在ではあまり使われていません。
遺言書は法的な文書であると同時に、家族への大切なメッセージでもあります。その中でも公正証書遺言は、形式や内容にしっかりとしたルールがあり、もっとも安心できる方法として、みらいえ相続でもおすすめしています。
もしものときに備えて、早めに準備を始めることが大切です。ご自身の気持ちをきちんと遺すためにも、相続の専門家に相談しながら進めていきましょう。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
第9話の終盤、物語の鍵となる3つの遺言書が登場します。羽毛田は、浅葉一族の闇を暴く情報を遺言書に託し、指定先に郵送した直後、何者かに襲撃され行方不明に。
灰江の母・深雪は、仏壇にしまっていた古びた遺言書を手にし、何かを決意します。さらに、令子の遺言書も加わり、それぞれの覚悟や想いが交錯。物語はいよいよ、真実と家族の絆が問われるクライマックスへと向かいます。

視聴者の疑問「複数の遺言書が見つかったらどうなるの?」
専門家の回答「法的に有効な新しい遺言書が優先されます。」
ドラマでは、令子、羽毛田、そして深雪がそれぞれの覚悟を記した遺言書が登場しました。また現実の相続では、1人の故人に複数の遺言書が見つかるケースも存在します。その場合、どの遺言書が有効なのかは以下のように判断されます。
1.日付の新しさが優先される
内容が異なる場合は、作成日が新しい遺言書が優先されます。
2.形式不備の遺言書は無効になる
署名や押印がないなど、法的な要件を満たしていない遺言書は無効と判断されます。
3.公正証書遺言はもっとも信頼性が高い
公証人が作成・保管するため、有効性の証明がしやすくトラブルも起きにくい形式です。
だからこそ、生前からしっかりと対策を講じておくことが重要です。遺言書の作成を含め、相続に関する準備は早めに進めておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。迷ったときは、相続の専門家に相談することをおすすめします。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。
最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。
しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。
だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。
第9話は、登場人物たちの覚悟や想いが「遺言書」という形で表現され、単なる相続の手続きではない心のメッセージとして描かれた印象的な回でした。羽毛田の決意、令子の命をかけた行動、そして深雪の静かな想い。それぞれの遺言書が、大切な人へ何を伝えたいのかを問いかけてきます。
遺言書はまだ早いと思いがちですが、この回を通して「家族のための準備」であり「自分の想いを残す手段」であることに気づかされます。相続を争いにしないためにも、自分の気持ちをどう遺すか、一度考えてみるきっかけになる1話でした。
相続における遺言書の役割は、法的効力だけにとどまりません。
家族が納得できる相続を実現するには「何を残すか」だけでなく「どう伝えるか」が非常に重要です。突然の事故や病気で意思が伝えられなくなる前に、遺言書や信託、生前贈与などの準備を始めておくことをおすすめします。
そして、自分だけで準備が難しいときは、税理士など相続の専門家のサポートを受けましょう。相続は一人の問題ではなく「家族の未来」そのもの。争族にならないための第一歩は「想いを言葉にすること」から始まります。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中