相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。

一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

佐藤 智春

日本では地価の上昇が続いており、それに連動して「路線価」も上がっています。路線価とは、国税庁が毎年公表する土地の評価額で、主に相続税や贈与税を計算する際の基準となるものです。
そのため、同じ土地でも路線価が上がれば相続税評価額が自動的に上昇し、固定資産税の負担も重くなる傾向があります。登録免許税、相続税なども含め、全体として税負担が増えているのが現状です。まさに「評価額も税負担も増える時代」といえるでしょう。
仙台でも駅周辺の再開発や都心回帰、インバウンド需要の回復により、商業地・住宅地の価値が押し上げられています。とくに実家が駅近や幹線道路沿い、再開発エリア周辺にある場合は、路線価の小さな上昇でも相続税評価や固定資産税が大きく変わることがあります。
こうした負担増に備える手段として有効なのが(小規模宅地等の特例)です。要件を満たせば、自宅や事業用の土地の評価額を大幅に引き下げ、相続税負担を抑えられます。
本記事では、地価・路線価・固定資産税の動向を踏まえつつ、小規模宅地等の特例の考え方と使い方を中心に、わかりやすく解説します。
相続で税額に大きな影響を与えるのは、一般に土地の評価です。土地は地域に応じて、国税庁が公表する路線価を基準に算定する路線価方式、または固定資産税評価額に倍率を掛ける倍率方式のいずれかで評価されます。
不動産は複数の評価方法や特例があるため、路線価や固定資産税評価額などを基準に計算すると、同じ金額の現金と比べて評価額が低くなるケースがあります。たとえば、小規模宅地等の特例を適用すれば最大80%減額できることもあり、結果的に相続税の負担を軽くできる可能性があるのです。

数字で見る全国と仙台の地価動向
路線価
令和7年分の全国平均は前年比+2.7%と、4年連続の上昇となりました。現行方式(2010年以降)で最大の伸びとされており、要因には訪日客需要の回復、駅周辺の再開発、都市居住志向の高まりなどが挙げられます。
国税庁|令和7年分の路線価等について
固定資産税
令和6年度の固定資産税収は9兆9,556億円(前年比+1.9%)で、3年連続の過去最高を記録しました。都市計画税も1兆4,402億円(+2.1%)と依然高水準にあります。
総務省|令和6年度地方税収入決算見込額
相続税
近年の相続税収はおおむね3兆円規模と高い水準で推移しており、地価の上昇や資産取引の活発化が背景にあるとされています。相続税の税率自体は変わっていませんが、地価の上昇に伴って路線価などの評価額が上がることで、課税対象となる資産額が増える傾向があります。
また、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)は平成27年の税制改正以降、据え置かれています。そのため、地価や資産評価が上昇する局面では、相対的に課税対象となる世帯が増えやすい仕組みになっています。
仙台の傾向
仙台でも駅周辺の再開発や都心回帰の動き、インバウンド需要の回復などにより、中心部や地下鉄沿線エリアを中心に地価の底上げ傾向がみられます。特に実家が駅徒歩圏、大規模再開発エリアの近隣、商店街や幹線道路沿いにある場合は、路線価の変化が相続税評価や固定資産税に影響を及ぼす可能性があります。郊外でも、生活利便施設の整備や新たな道路開通などによって路線価が見直されるケースが見られるため、地域特性に応じた確認が重要です。
不動産と現金の評価がもたらす相続への影響
不動産は、評価方法によって金額が変わる「一物多価」の性質を持っているため、現金と比べて相続時の評価額が低く算定されることがあり、その結果、相続税の節税につながる場合があります。代表的な評価基準は次のとおりです。
実勢価格(時価)
実際の市場で取引される価格です。
公示価格
国土交通省が毎年公表する標準的な価格です。
相続税路線価
相続や贈与時の評価基準で、一般的に公示価格のおおむね8割程度が目安とされています。
固定資産税評価額
固定資産税の算定基準となる価格で、一般的に公示価格のおおむね7割程度が目安です。
相続対策の第一歩は、現状を正しく数字化して把握することです。まずは「いま、うちの土地はいくらで評価されるのか」を確認し、基礎控除との関係や課税の可能性、納税資金を見える化することが大切です。
みらいえ相続グループでは、仙台の地域事情と最新の税制ルールを踏まえ、簡易な評価診断から課税影響の試算まで丁寧にサポートしています。早めに専門家へ相談することで、その後のプラン設計がぐっとスムーズになり、ご家族の安心につながります。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
不動産を相続する場合、小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や事業用の土地などについて、一定の要件を満たせば相続税評価額を大きく引き下げられる制度です。地価が上がりやすい地域では、適用の有無が相続税額を左右します。まずは、どういった土地がどのように扱われるのかという基本を押さえましょう。
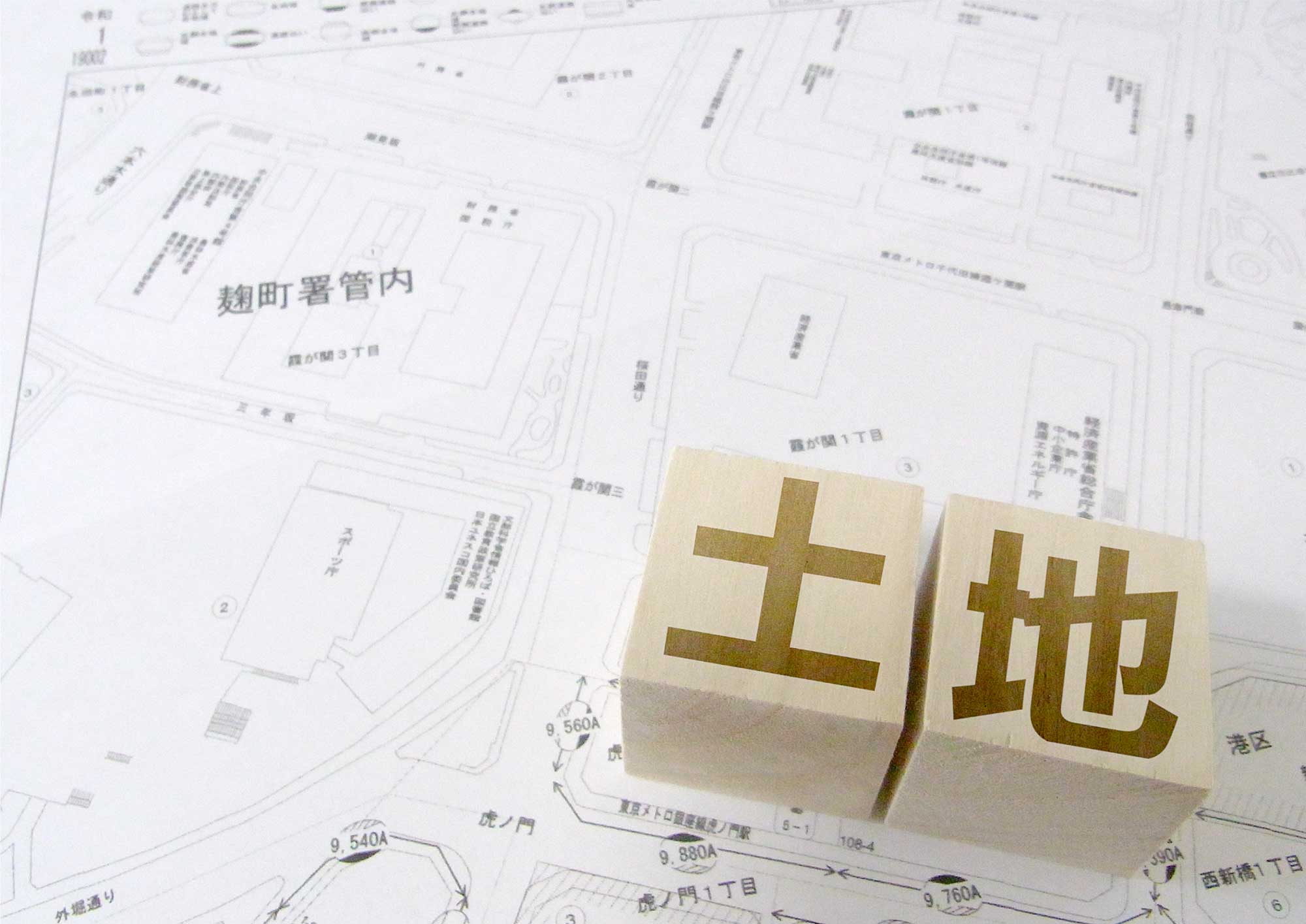
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、相続した宅地のうち一定の要件を満たすものについて、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。これは、残された家族の生活基盤や事業の継続を守るために設けられた制度で、相続人にとって大きな節税効果があります。宅地の利用区分ごとに減額割合・限度面積・適用条件が決められています。
① 特定居住用宅地等(居住用)
被相続人が居住していた自宅の宅地が対象です。
限度面積:330㎡
減額割合:80%減
② 特定事業用宅地等(事業用)
被相続人が営んでいた事業の用に供していた宅地が対象です。
限度面積:400㎡
減額割合:80%減
③ 貸付事業用宅地等(賃貸用)
被相続人が相続開始時点で行っていた賃貸事業に用していた宅地が対象です。
限度面積:200㎡
減額割合:50%減
④ 特定同族会社事業用宅地等
同族会社が事業の用に供している宅地が対象です。
限度面積:400㎡
減額割合:80%減
小規模宅地等の特例は、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定面積まで評価額を大幅に減額できる制度です。
制度の趣旨や要件を正しく理解し、相続される不動産が対象になるか、どの区分で適用できるか、申告までの手続きに漏れがないかについて、相続に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
不動産を相続する場合、小規模宅地等の特例は、制度を知っているだけでは足りません。小規模宅地等の特例は、実態(実際の利用)・証拠(それを示す資料)・期限(相続開始から10か月以内の申告)の三つがそろってはじめて適用されます。ここでは小規模宅地等の特例の適用要件とポイントについて説明します。

適用の前提
名義や登記だけでは足りず、実際に居住・事業・賃貸として使っていた事実を、住民票・帳簿・契約書などの客観資料で証明します。
居住用(特定居住用宅地等)
配偶者の取得は継続居住要件が不要、同居親族は申告期限まで居住継続が必要、「家なき子」は相続前3年以内の持家居住がない等の要件を満たし、住民票・郵便物送付先・公共料金の支払などで生活実態を示します。
事業用(特定事業用宅地等)
相続人が事業を承継し継続していることを前提に、青色申告書や帳簿、許認可、現場写真・取引書類で事業実態を証明します。
賃貸用(貸付事業用宅地等)
相続開始時点で被相続人が賃貸事業を行い相続後も継続していることを、賃貸借契約書・賃料入出金明細・入居者名簿・募集状況等で示します(コインパーキングなどの一時使用は原則自用地評価)。
注意点とポイント
申告は必須
小規模宅地等の特例を利用するには、相続税の申告が必ず必要です。
適用後に税額が0円となる場合でも、申告をしなければ特例は認められません。
期限は相続開始から10か月以内です。
売却や用途変更に注意
申告期限までに宅地を売却したり、居住用から賃貸用に転用した場合は特例の対象外となります。
居住や事業の継続が途切れる
相続人が居住を継続していない、または事業を承継・継続していないと適用できません。
「家なき子」要件の不備
相続開始前3年以内に本人または配偶者が持家に住んでいた場合は、特例の対象外となります。
持分や面積の不適合
相続人同士の分け方によって持分要件を満たさない場合や、面積が限度を超える場合は適用できません。
手続きの不備に注意
遺産分割の方法が適切でない場合や、必要書類に不備がある場合、特例は適用されません。
特に「同居していない子が相続する居住用宅地」や「貸付事業用宅地」は要件が厳格です。条件を満たしていなければ、特例を利用できない点に注意が必要です。
小規模宅地等の特例には、居住用330㎡・事業用400㎡・貸付事業用200㎡といった面積の上限があります。さらに、誰がどのように引き継ぐかといった実態や、登記・住民票・生計の整合性が適用の大きなポイントとなります。
生前からの計画と資料の準備を進めることで、安全かつ確実な相続税対策につなげることができます。必要に応じて、専門家とともにチェックリストを活用し、書類の整備を進めていくことをおすすめします。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。
最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。
しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。
だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。
相続では、不動産や登記の準備が欠かせません。相続登記は2024年4月から義務化されています。境界確定測量や共有名義の整理も、早めの対応が肝心です。さらに、一次相続だけでなく二次相続まで見据え、納税資金の確保も含めた設計が重要です。
不動産の評価は毎年変動します。とくに都市部の駅周辺や再開発エリアは影響が大きいため、定期的に状況を点検し、現状を数値で把握しておきましょう。あわせて、小規模宅地等の特例の活用などを組み合わせることが大切です。
みらいえ相続グループでは、税理士・行政書士・不動産の専門家が連携し、地域特性と最新のルールを踏まえたご提案を行っています。「我が家はいま、いくらで評価されるのか」。まずはここから確認してみませんか。どうぞお気軽にご相談ください。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中