相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。

一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

佐藤 智春

相続税の現場で最も申告漏れの指摘が多いのは、実は「現金・預貯金」です。タンス預金や名義預金は「見つからないだろう」という油断が生まれやすい一方で、税務署からは重点的に確認される領域でもあります。
国税庁が公表した令和5事務年度のデータによると、全国で行われた相続税の実地調査は8,556件。そのうち84.2%で申告漏れ(非違)が見つかっており、高い割合で修正が必要となっています。追徴税額は735億円にのぼり、さらに文書や電話による簡易な接触でも122億円が追徴されており、いずれも高水準です。
申告漏れが指摘された財産の内訳をみると、現金・預貯金等が約30.3%と最も大きな割合を占めています。特に「タンス預金」「名義預金」は、申告漏れ財産の代表格であり、税務署も徹底してチェックする対象です。
また、相続税の課税割合(課税対象者の比率)は9.9%に達しており、過去と比べても高い水準です。かつては一部の富裕層に限られていた相続税ですが、今ではより広く「誰にでも起こり得る税務リスク」になっていることがわかります。
本記事では、税務署がタンス預金を把握する主要なメカニズム、相続税調査の実態、そして「隠す」のではなく「見える化」して家族を守るための正しい生前対策を、相続専門家チームの視点から解説します。
国税庁|令和5年分相続税の申告事績の概要
国税庁|令和5事務年度における相続税の調査等の状況
「資産を現金で持っていれば記録が残らず、税務署にバレない」というのは、一般的によくある誤解です。実際には、国税庁の統計でも現金や預貯金が最も多く申告漏れとして指摘されており、決してバレないわけではありません。それでは税務署は何を見て、どうやって「見えない現金」をあぶり出すのでしょうか。仕組みを知れば、資産を隠すことの危うさが見えてきます。

税務署が資産を見抜く方法
KSK(国税総合管理)システム等による整合性チェック
国税庁には、被相続人の収入・資産・保険・不動産などの情報が一元管理されています。申告された財産額が過去の収入や資産の動きと大きく食い違えば、重点的に調べられます。
財務省|国税総合管理(KSK)システムの概要
金融機関照会と口座トレース(相続開始前10年分が目安)
相続人や被相続人の口座取引は、金融機関に照会されます。相続開始前10年間の預貯金について、大きな引き出しや不自然な振替、使途不明の出金がある場合は、タンス預金の存在を疑われる要因となります。
法定調書・反面調査による用途追跡
保険金や証券・不動産の取引は法定調書で把握されます。必要に応じて取引先に問い合わせ、資金の行方を確認します。売却したはずの資金が行き先不明なら、現金化して手元に残していると疑われます。
実地調査(自宅)での現物・資料確認
自宅や貸金庫で、通帳・証書・印鑑・現金・金庫の中身などを調べます。押入れや仏壇など「隠しやすい場所」も確認対象です。また、子や孫名義でも実際には本人が管理している「名義預金」も調査されます。
家計収支と生活実態からの整合性評価
収入と支出のバランスを見て、不自然に多い現金の引き出しが続いていないか確認します。生活実態に合わない出金があれば、タンス預金を疑われやすくなります。実際に令和5年度の調査では、84.2%に申告漏れが見つかり、漏れの多くが現金・預貯金でした。「隠せば大丈夫」という考えは非常に危険です。
国税庁|令和5年分相続税の申告事績の概要
国税庁|令和5事務年度における相続税の調査等の状況
タンス預金は違法ではありませんが、相続で申告しないことは脱税になり得ます。税務当局は、データ突合・金融照会・反面調査・実地調査を組み合わせて現金の行方を確認します。見つかった場合は加算税・延滞税、悪質なら重加算税の対象です。結局、「隠す」より「見える化」が最も安全で、家族を守る最も確実な方法です。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
相続税の調査では、多くのケースで申告漏れが指摘され、追徴課税に発展しています。中でも現金や預貯金は申告漏れ財産の代表格であり、特に注意が必要です。相続は誰にでも起こり得るものであり、現金を中心とした財産管理の不備は大きな税務リスクにつながります。
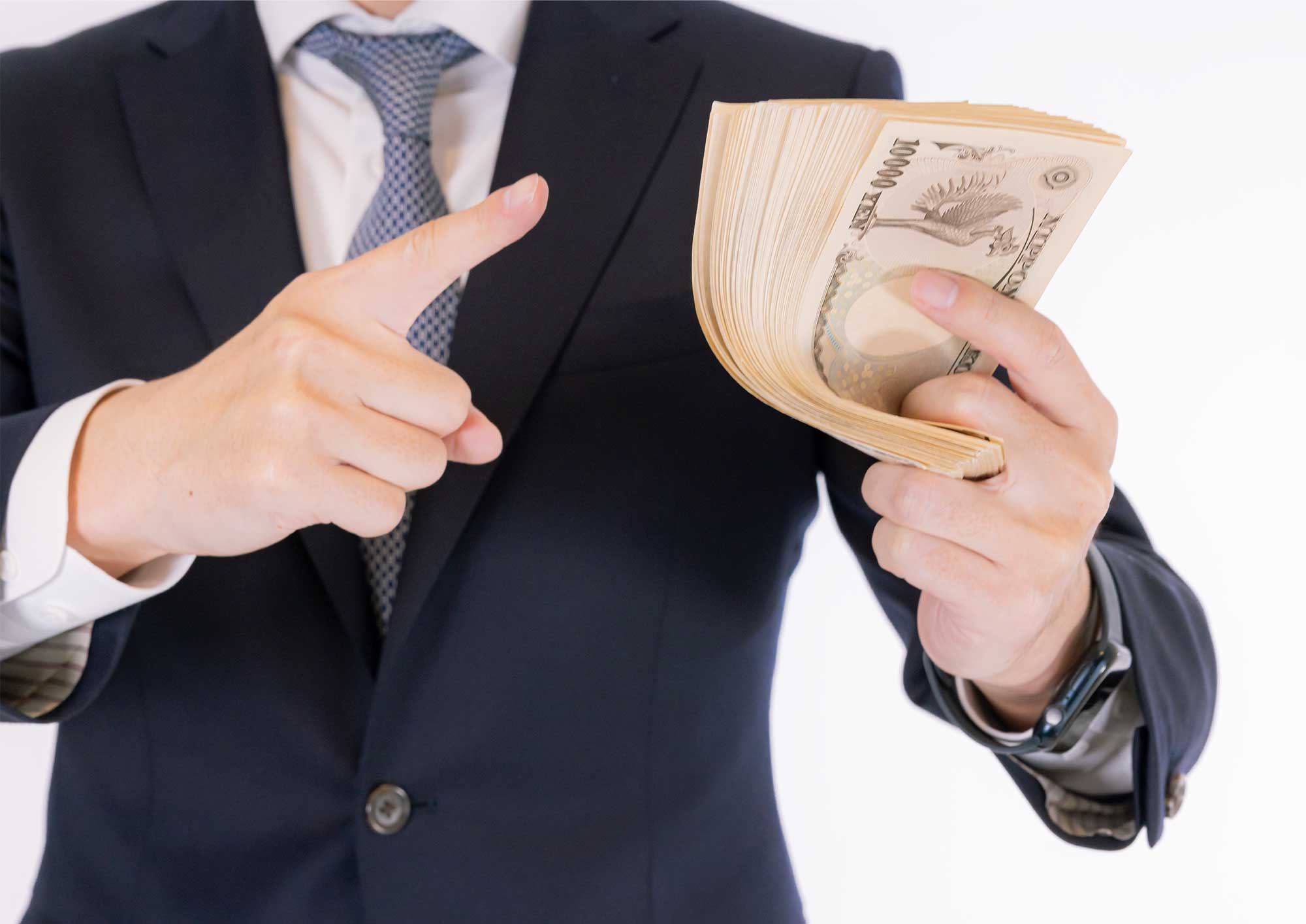
調査で見られやすい現金・預貯金のポイント
税務署は特に以下のような取引や状況を重点的に確認します。
相続開始前10年間の預貯金の大きな引き出しや使途不明のお金
相続の前後に不自然に移動した資金
(急に相続人名義の口座に入金、貸金庫を解約して資金が動くなど)
名義預金の疑い
(名義は子や孫でも、実際は被相続人が管理している場合)
生活水準に合わない多額の現金保有
申告されていない高額購入の形跡
(貴金属や車を現金で購入しているのに申告されていない場合など)
調査のタイミングと範囲
申告から1~2年後に実地調査が行われるケースが多くあります(全件ではありません)。口座照会は相続開始前10年分が目安とされます。
申告漏れが見つかった場合の主なペナルティ
申告漏れが確認された場合、以下のような加算税や延滞税が課されます。悪質な場合には、刑事罰が科される可能性もあります。
過少申告加算税
新たに納める税額に対し原則10~15%(修正のタイミングによって軽減あり)
無申告加算税
5~30%(自主的な期限後申告で軽減)
重加算税
悪質な隠蔽・仮装が認定されると35%(期限内申告)、40%(無申告)
延滞税
納付遅延に対する利息相当で、税率は特例基準割合に連動し、2か月以内とそれ以上で区分されます
隠して節税するという考え方は通用せず、発覚すれば加算税や延滞税、重加算税によってかえって大きな負担につながります。特に相続税の基礎控除に近いケースは、財産評価や申告の有無で課税・非課税が分かれるため、税務署が「見落としや申告漏れがないか」を重点的に確認する場合があります。だからこそ、生前のうちから財産を見える化し、整理し、説明できる状態を整えておくことが重要です。
みらいえ相続グループでは、税理士・行政書士・不動産の各専門家が連携し、相続に関するあらゆる課題をトータルでサポートしています。相続税申告や生前贈与、財産評価の見直しに加え、遺言書や家族信託の作成を通じて、将来の争いを防ぐ仕組みも整えます。
さらに、不動産についても活用・売却・分割に至るまで実務的なアドバイスを提供しています。税金対策から法律手続き、不動産整理まで一貫して支援できることが、私たちの大きな強みです。相続に不安を抱える方も、事前に準備を進めたい方も、どうぞ安心してご相談ください。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
相続税申告をスムーズに行うためには、生前のうちからしっかりと準備しておくことが大切です。大切なのは、財産を明確にし、無駄な税負担を避けつつ、円滑に相続できる体制を整えることです。
そのために、ご家庭ごとの資産状況や家族構成、そして大切にしたい価値観に合わせて、トラブル防止、節税、納税資金の確保、さらには将来への備えまでを一体的に設計していくことが求められます。

財産目録と資金の流れを整えることが大切
まずは、現金・預貯金・証券・保険・不動産・事業資産・貸付金などの財産をリスト化し、それぞれの評価や所在、根拠となる資料をきちんと紐付けて管理します。現金は銀行などで管理し、出金した場合には使途をメモに残しておくことが重要です。
特に死亡直前の出金については、後に説明できるように意識して記録を残す必要があります。また、名義預金と誤解されないようにするためには、贈与の際に振込み作業は贈与者が行う、普段使いの通帳に振り込む、引き出し作業は口座名義人が行う等、管理も明確に区分することを徹底することが大切です。
トラブルを防ぐための対策
遺言(推奨:公正証書遺言)
遺言を作成しておくことで、遺産の分け方を明確にすることができます。特に公正証書遺言であれば法的な効力が強く、相続人同士の争いを避けやすくなります。
関連資料|みらいえ相続の遺言サービス(PDF)
家族信託
認知症対策や長期的な財産管理に備えて、財産の運用や処分を信頼できる家族に託すことができます。将来にわたる財産の管理を任せられるだけでなく、二次相続先を指定できるため、長期的な資産承継の設計にも役立ちます。
任意後見
判断能力が低下した後も、生活費の支払いや契約の手続きをスムーズに進められるようにする制度です。必ず元気なうちに契約を結んでおく必要があります。
その他
エンディングノートを作成し、相続や医療、葬儀に関する希望を記録しておけば、家族が迷わず対応でき、トラブル防止につながります。財産の所在や連絡先に加え、ネット銀行や証券口座、電子マネー、SNSなどのデジタル資産の情報も整理しておくと安心です。
節税のための対策
生前贈与
暦年贈与や相続時精算課税制度を活用することで、相続財産を前もって移転させることができます。その際には、贈与契約書を作成し、資金移動の実態を明確に整備することが大切です。なお、相続直前の贈与は効果が薄れる場合があるため、注意が必要です。
生命保険
生命保険には「法定相続人の数×500万円」の非課税枠があり、これを活用することで節税が可能です。さらに、死亡保険金は納税資金としても役立ちます。誰を受取人にするかを最適に設定することが重要なポイントです。
資産の組み換え
分割しにくい不動産をそのまま残すと相続人同士のトラブルや納税資金不足につながる可能性があります。あらかじめ売却や区分を行い、分割しやすい形にしておくと安心です。その際には、譲渡所得税や諸費用を事前に試算しておくことが大切です。
納税資金の対策
相続税の納付を期限内に行うためには、現金・生命保険・資産の売却計画を組み合わせて準備しておくことが大切です。延納や物納といった制度もありますが、利用には条件があるため、生前のうちに要件を確認しておく必要があります。
生前対策の本質は、財産の透明性・公平性を確保し、将来の資金計画をしっかり整えることにあります。金融機関での適切な管理や記録の整備、贈与や信託の活用を通じて、安心して次世代へ財産を引き継ぐことができます。
みらいえ相続グループでは、税理士・行政書士・不動産部門が連携し、トラブルの回避、適正な課税、納税資金の確保をバランスよく実現できる対策をご提案しています。相続税申告については豊富な経験を持つ専門税理士が、お客様を丁寧にサポートいたします。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。
最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。
しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。
だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。
相続税調査では、現金・預貯金が最も申告漏れを指摘されやすく、「隠す節税」はかえって加算税や延滞税などによる大きな負担につながります。大切なのは、財産を正しく見える化し、必要な書類を整備し、早めに対策を設計することです。
みらいえ相続グループは、税理士・行政書士・不動産の専門家が連携し、相続のトラブル防止、節税、納税資金の準備をワンストップでサポートしています。税務・法務・不動産を総合的に組み合わせることで、ご家族の状況に合わせた最適な対策をご提案することが可能です。「何から始めればよいのか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

どんな相続のお悩みも
ご相談ください
相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。
初回
無料
相続のご相談ならお気軽に
面談受付中