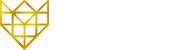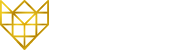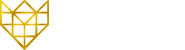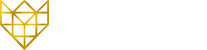不動産名義変更
不動産を相続した時に必要な
名義変更手続き
01名義変更の基礎知識
不動産の相続手続きにおいて、名義変更(相続登記)は非常に重要な手続きです。名義変更を正確に行うことで、相続人の権利を明確にし、不動産に関連するリスクを未然に防ぐことができます。
相続登記の法的義務化について
2024年4月1日より、不動産の相続登記が法的に義務化されました。この改正により、相続による不動産の名義変更を行わない場合、一定の罰則が科される可能性があります。
● 法改正の背景
名義変更が行われない不動産が増加し、所有者不明土地問題が深刻化していることを受け、相続登記の義務化が実施されました。
● 義務化の対象
相続による不動産の名義変更が対象となります。生前贈与や売買による登記変更は対象外です。
期限と罰則について
相続登記には期限が定められており、期限を守らない場合には罰則が適用される可能性があります。
● 法定期限
相続開始を知った日(通常は被相続人が死亡した日)から3年以内。
● 罰則
登記未了の場合、過料(最大10万円)が科される可能性があります。ただし、正当な理由がある場合は免除される場合もあります。
名義変更が必要な不動産の種類
名義変更が必要な不動産には、以下のようなものが含まれます。これらの不動産が遺産として残された場合、名義変更を行う必要があります。
| 不動産の種類 | 具体例 |
| 土地 | 宅地、農地、山林、原野など |
| 建物 | 一戸建て、マンションの専有部分、倉庫など |
| 一部権利の共有不動産 | 共有持分がある土地や建物など |
不動産の種類によって必要な手続きや書類が異なる場合があります。事前に不動産の状況を確認し、適切な対応を進めることが重要です。
02名義変更の期限
不動産の名義変更(相続登記)は、法律で定められた期限内に行う必要があります。期限を守らない場合、罰則が科される可能性があるため、早めの手続きを心がけましょう。また、正当な理由がある場合には期限の延長が認められるケースもあります。
法定期限(3年以内)の場合
2024年4月1日以降、相続登記は被相続人の死亡を知った日から3年以内に行うことが義務付けられました。この期限内に手続きを行わないと、過料が科される場合があります。
● 法定期限の具体例
被相続人が2025年4月1日に亡くなった場合、相続登記の期限は2028年4月1日までとなります。
● 期限遵守の重要性
名義変更を行わない場合、不動産の売却や譲渡が制限されるほか、相続人間でトラブルが発生するリスクが高まります。
正当な理由がある場合の延長
正当な理由がある場合には、相続登記の期限が延長されることがあります。延長が認められるケースには以下のようなものがあります。
| 正当な理由 | 詳細 |
| 相続人が所在不明 | 特定の相続人が行方不明の場合、所在確認や裁判所での手続きが必要になるため延長が認められる可能性があります |
| 遺産分割協議が未完了 | 相続人間の話し合いがまとまらず、遺産分割協議が完了していない場合には期限延長が認められることがあります。 |
| 書類の準備が遅延 | 戸籍謄本や登記識別情報の取得に時間がかかる場合、延長が認められる場合があります。 |
延長を希望する場合は、法務局や専門家に相談し、状況に応じた対応を行いましょう。
期限を過ぎた場合の対応
期限を過ぎた場合でも、罰則を回避するための対応が可能です。ただし、早急に手続きを進める必要があります。
● 過料のリスク
期限を過ぎると、過料(最大10万円)が科される可能性があります。ただし、申請の遅延理由が正当と認められる場合、過料が軽減または免除されることがあります。
● 手続きの優先事項
- 必要書類を早急に準備し、法務局に相続登記を申請します。
- 手続きの遅延理由を説明する書類を用意することで、過料の免除が認められる可能性が高まります。
03名義変更に必要な書類
基本的な必要書類
不動産の名義変更(相続登記)を行う際には、必要書類を正確に準備することが重要です。以下に、一般的に求められる基本的な書類を詳しく解説します。
戸籍謄本・除籍謄本一式
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および除籍謄本を用意します。これにより、相続人の範囲が確定します。
● 取得先
市区町村役場で取得可能です。被相続人の本籍地を事前に確認しておくとスムーズです。
● 注意点
必要な期間の戸籍を全て揃える必要があるため、抜け漏れがないように注意してください。
相続人全員の住民票
相続人全員の住民票が必要です。名義変更後の新しい所有者を証明するために使用します。
● 取得先
各相続人の住所地を管轄する市区町村役場で取得します。
● 注意点
住民票にはマイナンバーが記載されないように注意し、窓口でその旨を伝えましょう。
印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書を用意します。遺産分割協議書の作成や法務局への提出時に必要となります。
● 有効期限
発行日から3ヶ月以内のものが求められるため、手続き直前に取得してください。
● 注意点
各相続人の住所地を管轄する市区町村役場で取得可能です。
固定資産評価証明書
不動産の評価額を証明する書類です。名義変更時の登録免許税を計算する際に使用します。
● 取得先
不動産所在地の市区町村役場または都道府県税事務所で取得可能です。
● 注意点
取得年度の最新の評価証明書を用意してください。
登記識別情報(旧権利証)
登記済みの不動産について、所有権を証明する書類です。2005年以降に登記された不動産では「登記識別情報」と呼ばれる12桁の番号が発行されています。
● 保管場所の確認
被相続人が保管している場合が多いため、家族で確認しましょう。
● 注意点
紛失している場合は、登記申請時に法務局で「事前通知制度」などを利用して手続きを進めます。
| 書類名 | 用途 | 取得先 | 注意点 |
| 戸籍謄本・除籍謄本一式 | 被相続人の出生から死亡までの記録を確認し、相続人を確定するため | 被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場 | 期間を網羅した戸籍を全て揃えること。抜け漏れに注意。 |
| 相続人全員の住民票 | 名義変更後の新しい所有者を証明するため | 各相続人の住所地を管轄する市区町村役場 | マイナンバーが記載されないよう窓口で伝えること。 |
| 印鑑証明書 | 遺産分割協議書や法務局提出書類に添付するため | 各相続人の住所地を管轄する市区町村役場 | 発行日から3ヶ月以内のものが有効。取得時期に注意。 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産の評価額を証明し、登録免許税の計算に使用 | 不動産所在地の市区町村役場または都道府県税事務所 | 最新年度のものを取得。物件ごとに必要になるため、複数ある場合は全て揃える。 |
| 登記識別情報(旧権利証) | 不動産の所有権を証明するため | 被相続人の保管場所、または法務局 | 紛失している場合は「事前通知制度」などの代替手続きを利用可能。 |
注意
- 必要書類は相続する不動産の種類や相続形態により異なる場合があります。事前に確認して、追加書類が必要な場合は早めに準備を進めてください。
- 書類の取得には手数料がかかることがあります。各自治体の料金を確認しておきましょう。
- 書類の内容に不備があると手続きが遅れるため、提出前に内容をしっかり確認してください。
04相続形態別の追加書類
相続する不動産の名義変更には、基本的な書類に加えて、相続形態に応じた追加書類が必要です。それぞれの相続形態ごとに必要な書類とそのポイントを以下にまとめます。
| 相続形態 | 必要書類 | 用途 | 注意点 |
| 遺産分割協議の場合 | 遺産分割協議書 | 相続人間で遺産の分配方法を合意したことを証明するため | 相続人全員の署名・押印が必要。不備があると手続きが進まないため慎重に作成すること。 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書の署名・押印の真正性を確認するため | 発行日から3ヶ月以内のものを用意。不動産の種類や数に応じて複数枚必要になる場合がある。 | |
| 遺言相続の場合 | 遺言書 | 被相続人が残した遺産分配の意思を示した文書 | 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要。公正証書遺言の場合はそのまま使用可能。 |
| 検認調書 | 自筆証書遺言を家庭裁判所で検認したことを証明する書類 | 検認後に発行されるため、検認手続きが完了してから取得する必要があります。 | |
| 法定相続の場合 | 法定相続情報一覧図 | 法定相続分に基づく相続手続きを進めるため | 法務局で作成し、相続手続きの効率化に使用可能。不動産が複数ある場合でも一覧図1枚で対応可能。 |
各相続形態のポイント
- 遺産分割協議の場合
相続人間で協議を行い、全員の同意を得た内容を遺産分割協議書に記載します。作成時に専門家(司法書士や行政書士)のサポートを受けると、法的に正確な文書を作成できます。 - 遺言相続の場合
公正証書遺言がある場合は検認が不要で、遺言書の内容に従って手続きを進めます。一方、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要となるため、手続きがやや複雑になります。 - 法定相続の場合
法定相続分に基づいて手続きを進める場合、法定相続情報一覧図を作成すると、必要書類が簡略化されます。この一覧図は、法務局で作成手続きを行うことで取得できます。
05具体的な手続きの流れ
事前準備
不動産名義変更の手続きを円滑に進めるためには、事前準備が非常に重要です。不動産の権利関係を確認し、必要な情報を揃えることで、次のステップをスムーズに進めることができます。
不動産の権利関係確認
まず、相続する不動産の権利関係を確認します。これにより、名義変更に必要な書類や手続きが明確になります。
● 確認内容
- 不動産が共有名義でないか。
- 抵当権や地役権などの権利が設定されていないか。
- 被相続人以外の権利者が存在しないか。
● 注意点
権利関係に問題がある場合は、事前に解決しておく必要があります。不明点がある場合は専門家に相談することをおすすめします。
登記事項証明書の取得
不動産の現在の状況を確認するために、登記事項証明書(旧登記簿謄本)を取得します。これには、不動産の権利や所有者情報が記載されています。
● 取得先
管轄の法務局またはオンライン申請サービス(登記・供託オンライン申請システム)を利用します。
● 取得に必要な情報
不動産の所在地や地番を正確に把握しておく必要があります。
● 注意点
記載内容に誤りがある場合は、早急に修正手続きを進める必要があります。
相続人の確定
相続人を確定させることで、名義変更手続きに必要な書類が明確になります。相続人を確定するためには、被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで揃える必要があります。
● 確認内容
- 相続人全員の範囲(配偶者、子ども、直系尊属など)を確認。
- 特別な条件(養子縁組、離婚歴など)がある場合は追加書類を確認。
● 注意点
相続人間で意見の相違がある場合は、遺産分割協議書を作成して合意を得る必要があります。
必要書類の収集
不動産名義変更の手続きを進めるには、必要な書類を正確に揃えることが不可欠です。この段階では、戸籍関係書類の収集、相続人の意向確認、そして遺産分割協議書の作成を行います。これらの手続きが適切に行われることで、名義変更の申請がスムーズに進みます。
戸籍関係書類の収集
戸籍関係書類は、被相続人や相続人の関係を証明するために必要です。これらの書類を漏れなく揃えることで、相続人の範囲を確定できます。
● 必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および除籍謄本
- 各相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
● 取得先
被相続人の本籍地や相続人の住所地を管轄する市区町村役場で取得可能です。
● 注意点
書類の不備があると手続きが遅れるため、収集時に窓口で漏れがないか確認してください。
相続人の意向確認
相続人全員の意向を確認し、不動産をどのように分割・所有するかを決定します。このプロセスは、相続人間での合意形成において重要です。
● 確認内容
- 不動産を売却するのか、共有名義とするのか、特定の相続人が単独で相続するのか。
- 登録免許税や不動産の維持費などの負担割合。
● 注意点
意向がまとまらない場合は、遺産分割協議が長引く可能性があります。必要に応じて専門家を交えて協議を進めましょう。
遺産分割協議書の作成
相続人全員の同意内容を記載した遺産分割協議書を作成します。この書類は、名義変更手続きにおける重要な証拠となります。
● 作成手順
- 相続財産の内容と分割方法を具体的に記載します。
- 相続人全員が署名・押印を行い、印鑑証明書を添付します。
● 注意点
法的に有効な書類を作成するために、司法書士や行政書士のサポートを受けることをおすすめします。
登記申請
不動産名義変更の手続きの中核となるのが、法務局への登記申請です。申請方法にはオンライン申請と窓口申請があり、それぞれにメリットと注意点があります。必要書類を揃えたうえで、適切な方法を選択し、手続きを進めましょう。
法務局への申請方法
不動産の所在地を管轄する法務局で名義変更の登記申請を行います。手続きの正確性が求められるため、提出書類に不備がないかを事前に確認することが重要です。
● 必要書類の確認
- 基本的な必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書、固定資産評価証明書など)
- 相続形態に応じた追加書類(遺産分割協議書、遺言書、法定相続情報一覧図など)
● 申請先の特定
不動産の所在地を管轄する法務局を確認してください。複数の不動産が異なる管轄にある場合、それぞれの法務局に申請する必要があります。
オンライン申請の手順
法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」を利用すると、登記申請をオンラインで行うことができます。手続きの効率化を図りたい場合に有効な方法です。
- システム登録
登記・供託オンライン申請システムにアクセスし、ユーザー登録を行います。 - 申請データの入力
名義変更に必要な情報をシステム上で入力し、必要書類をスキャンしてアップロードします。 - 申請料の納付
電子納付システムを利用して、登録免許税などの申請料を支払います。 - 申請完了と進捗確認
申請完了後、システム上で進捗状況を確認することができます。必要に応じて追加書類をオンラインで提出します。
● 注意点
システム操作に慣れていない場合、誤入力が生じる可能性があるため、慎重に操作してください。
窓口申請の手順
従来の方法である窓口申請では、書類を直接法務局に持参して提出します。担当者と対面で確認ができるため、書類不備を防ぎやすいという利点があります。
- 必要書類の準備
法務局指定の様式に従って申請書を作成し、必要書類を添付します。 - 窓口での提出
管轄の法務局窓口で書類を提出します。担当者が書類の確認を行い、不足や不備がある場合はその場で指摘されます。 - 申請料の納付
窓口で登録免許税を支払います。収入印紙での納付が一般的です。 - 完了確認
手続き完了後、登記完了証が発行されます。この証明書を受け取り、手続きが完了します。
● 注意点
混雑している場合、待ち時間が発生することがあります。事前予約が可能な場合は活用するとスムーズです。
登記完了後の対応
不動産名義変更の登記が完了した後も、必要な手続きが残っています。登記完了証の確認や固定資産税の名義変更、関連機関への届出を確実に行うことで、不動産の管理や税務対応がスムーズになります。
登記完了証の確認
登記手続きが完了すると、法務局から登記完了証が発行されます。この証明書は、名義変更が正しく行われたことを示す重要な書類です。
● 確認内容
- 不動産の所有者情報が相続人に変更されているか確認します。
- 登記内容に誤りがないかを確認し、不明点があれば法務局に問い合わせます。
● 保管方法
登記完了証は、不動産の所有権を証明する重要な書類のため、安全な場所に保管してください。デジタル形式で発行される場合もあるため、電子データのバックアップも検討しましょう。
固定資産税の名義変更
固定資産税の納税通知書は、新たな所有者に送付されるように名義変更を行う必要があります。固定資産税の名義変更を忘れると、税金の通知が被相続人宛てに送られ、相続人が把握できないリスクがあります。
● 手続き内容
- 不動産所在地を管轄する市区町村役場で名義変更手続きを行います。
- 必要書類として、登記完了証や戸籍謄本が求められる場合があります。
● 注意点
手続きが完了するまでに時間がかかる場合があるため、早めに市区町村役場に問い合わせておくことをおすすめします。
関連機関への届出
名義変更後は、不動産に関連するさまざまな機関へ届出を行います。これにより、不動産の管理や利用が適切に行えるようになります。
● 主な届出先
- 水道局・ガス会社・電力会社:契約名義の変更を行い、料金通知先を新所有者に変更します。
- 金融機関:不動産に関連するローンや担保がある場合、名義変更内容を金融機関に通知します。
- 自治体の土地台帳課:土地台帳の所有者情報を更新します。
● 注意点
各機関ごとに必要書類や手続き内容が異なるため、事前に確認し、書類を揃えてから手続きを進めてください。
06名義変更の費用
登記費用の内訳
不動産名義変更にかかる費用の中で、最も大きな割合を占めるのが登記費用です。登録免許税や評価額の確認、場合によっては軽減措置の適用が必要です。それぞれのポイントを以下で詳しく解説します。
登録免許税の計算方法
登録免許税は、名義変更の際に法務局に支払う税金です。不動産の評価額に基づいて計算されます。
● 計算式
登録免許税額 = 固定資産税評価額 × 0.4%(相続による名義変更の場合)
● 例
固定資産税評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円となります。
● 支払い方法
法務局窓口で収入印紙を購入して支払います。
評価額の確認方法
登録免許税を計算するためには、不動産の固定資産税評価額を確認する必要があります。
● 確認書類
固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書に記載されています。
● 取得先
不動産所在地の市区町村役場または都道府県税事務所で発行可能です。
● 注意点
年度によって評価額が異なるため、最新年度の評価証明書を取得してください。
軽減措置について
一定の条件を満たす場合、登録免許税が軽減される措置が適用されることがあります。適用条件や申請方法を確認し、軽減措置を活用することで費用を抑えることが可能です。
| 軽減措置の種類 | 適用条件 | 軽減内容 | 必要書類 |
| 居住用住宅の相続軽減措置 | 被相続人が亡くなるまで実際に居住していた住宅を相続する場合 | 登録免許税が通常の0.4%から0.3%に軽減 |
|
| 土地に関する軽減措置 | 特定の要件を満たす土地(相続税評価額が低くなる特例の対象地など)を相続する場合 | 登録免許税の一部または全額免除が適用される場合がある |
|
| 一定の年数を経過した住宅 | 築年数が一定以上で、耐震改修工事が行われた住宅を相続する場合 | 登録免許税が軽減される場合がある |
|
07その他の諸費用
不動産名義変更には登記費用以外にもさまざまな諸費用がかかります。これらの費用を事前に把握しておくことで、手続き全体の予算を明確にすることができます。以下に、必要書類の取得費用、専門家への依頼費用、印紙代や郵送費などの詳細を解説します。
| 費用項目 | 詳細 | 目安金額 | 備考 |
| 必要書類の取得費用 | 戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書など、名義変更手続きに必要な書類を取得する費用。 | 1通あたり300~1,000円程度 | 書類の種類や発行元自治体によって異なる場合があります。 |
| 専門家への依頼費用 | 司法書士や行政書士に手続きを依頼する場合の報酬。書類作成や法務局への申請代行を依頼するケースが一般的。 | 50,000~150,000円程度 | 不動産の数や相続形態の複雑さに応じて費用が変動します。 |
| 印紙代・郵送費等 | 法務局への書類提出時に必要な郵送費や、登記申請書に貼付する収入印紙代など。 | 収入印紙:4,000~10,000円程度 郵送費:500~1,000円程度 |
複数の不動産を一度に申請する場合、印紙代が増加する可能性があります。 |
必要書類の取得費用
名義変更に必要な書類は、戸籍謄本や固定資産評価証明書など多岐にわたります。書類ごとに取得費用が異なるため、取得する書類を事前にリストアップし、費用を計算しておくと安心です。
専門家への依頼費用
手続きをスムーズに進めるために、司法書士や行政書士に依頼するケースが多いです。専門家に依頼することで、書類の不備や申請ミスを防ぎ、効率的に名義変更を進められます。
印紙代・郵送費等
登記申請には収入印紙が必要です。また、法務局へ書類を郵送する場合は郵送料も発生します。複数の不動産を申請する場合や追加書類が必要な場合には、これらの費用が増加する可能性があるため、予算に組み込んでおきましょう。
08特殊なケースへの対応
不動産名義変更の手続きは、相続の内容が複雑な場合、特別な対応が必要になることがあります。相続人が多数いる場合や相続放棄がある場合、さらには所在不明者がいる場合など、それぞれのケースに応じた適切な手続きを理解して進めることが重要です。
相続人が多数の場合
相続人が複数いる場合、名義変更手続きは合意形成が鍵となります。全員の意向を調整しながら進める必要があります。
● 対応手順
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、内容を明確化します。
- 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
- 必要書類を揃え、法務局に名義変更を申請します。
● 注意点
相続人全員の同意が得られない場合、家庭裁判所で調停を行う必要があります。
相続放棄がある場合
相続放棄を行った相続人がいる場合、その相続分が他の相続人に移るため、名義変更手続きに影響があります。
● 対応手順
- 相続放棄を証明する書類(家庭裁判所の受理証明書)を取得します。
- 他の相続人で遺産分割協議を行い、協議書を作成します。
- 必要書類を揃え、名義変更手続きを進めます。
● 注意点
相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
所在不明者がいる場合
相続人の中に所在不明者がいる場合、名義変更手続きは複雑化します。所在不明者の代理人を選任するなどの対応が求められます。
● 対応手順
- 可能な限り所在不明者の連絡先を調査します。
- 所在が特定できない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
- 選任された代理人とともに遺産分割協議を進めます。
● 注意点
所在不明者がいる場合、手続きが長期化する可能性が高いため、早めの対応が必要です。
不動産名義変更は早めの準備と適切な対応が必要
相続による不動産名義変更は、相続人の権利を確定し、不動産を適切に管理するために欠かせない手続きです。2024年4月以降、相続登記が法的に義務化され、期限内に手続きを完了しないと罰則が科される可能性があります。名義変更には、戸籍謄本や固定資産評価証明書などの必要書類を揃え、相続形態に応じた追加書類を準備することが重要です。法務局での登記申請はオンラインまたは窓口で行うことができ、完了後には固定資産税の名義変更や関連機関への届出も必要です。
相続人が多数いる場合や相続放棄がある場合、さらには所在不明者がいる場合には特別な対応が求められるため、計画的な進行が不可欠です。また、登録免許税の軽減措置を活用することで費用を抑えることが可能です。不動産名義変更は複雑に感じるかもしれませんが、手順を整理し、専門家のアドバイスを活用することでスムーズに進められます。早めの準備と適切な対応で、トラブルのない相続手続きを実現しましょう。
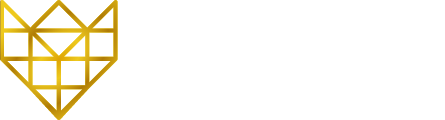
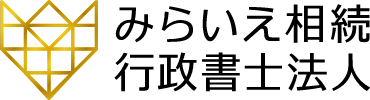



 相続相談に関するご予約
相続相談に関するご予約  0120-957-339
0120-957-339