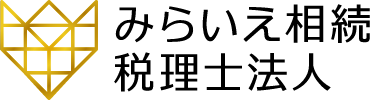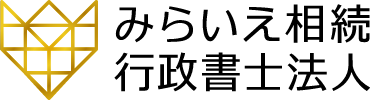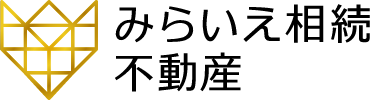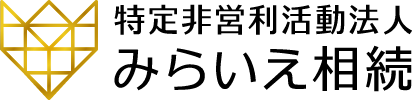よくあるご質問
相続手続き
Q.相続手続きはいつから始めればよいですか?
相続手続きは、被相続人(亡くなった方)が亡くなられた日を起点として進めていく必要があります。初めに行うべきことは、相続人の確定と遺産の内容の把握です。特に、相続放棄や限定承認を希望する場合は、相続の開始を知ってから3か月以内に手続きを行う必要があるため、早めに着手することをおすすめします。
Q.相続手続きに必要な書類は何ですか?
相続手続きに必要な主な書類は以下の通りです。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
・相続人全員の戸籍謄本および住民票
・遺産分割協議書
・不動産の登記事項証明書
・預貯金の残高証明書
これらの書類は、手続きの種類(不動産登記、金融機関手続き、相続税申告など)によって異なる場合があるので、専門家に確認することをおすすめします。
Q.相続人全員の同意が得られない場合、どうすればよいですか?
相続人全員の同意が得られない場合、遺産分割協議は成立しません。この場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、第三者の調停委員を交えて話し合いを進めることができます。それでも解決しない場合は「審判」に移行し、裁判所が最終的な判断を下すことになります。
Q.相続放棄の手続きはどのように行いますか?
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出して行います。申述書には、被相続人の戸籍謄本や相続人自身の住民票などの書類を添付します。期限を過ぎると単純承認(すべての財産を相続すること)となるため、早めの手続きが必要です。
Q.遺言書がない場合、相続はどのように進めればよいですか?
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、各手続きを進めていきます。相続人間での意見がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することもできます。
相続税申告
Q.相続税の申告期限はいつですか?
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなられた日の翌日から10か月以内です。申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があるため、期限内に申告することが重要です。
Q.相続税がかかる財産の基準額はいくらですか?
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円です。これを超える財産を相続する場合、相続税の申告が必要になります。
Q.相続税の計算方法を教えてください。
相続税の計算は、まず相続財産の評価額を算出し、そこから基礎控除額を引きます。その差額に応じた税率(10%~55%)を掛け算し、さらに各種控除を適用して最終的な税額を計算します。詳細な計算は専門的な知識が必要なため、税理士に相談することをお勧めします。
Q.相続税の納付方法にはどのような選択肢がありますか?
相続税の納付方法には、現金一括納付のほか、物納(財産で納める方法)や延納(分割払い)が選択できます。延納は一定の要件を満たす場合に限り認められ、申告書とともに延納申請書を提出する必要があります。
Q.相続税の申告を忘れた場合、どうなりますか?
相続税の申告期限を過ぎた場合、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。また、相続税の追徴課税を受ける可能性もありますので、期限を過ぎた場合は速やかに税務署に相談し、対応することをお勧めします。
不動産相続
Q.相続した不動産の登記はいつまでに行う必要がありますか?
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続が発生した日から3年以内に行う必要があります。また登記を行わないと第三者に権利を主張できず、不動産の売却や担保設定ができないほか、相続人間でのトラブルの原因となることがあります。
Q.相続した不動産を売却する場合の税金はどうなりますか?
相続した不動産を売却した場合、「譲渡所得税」がかかる可能性があります。譲渡所得は売却価格から取得費や譲渡費用を引いた額に対して課税され、相続により取得した不動産の場合、特例として「取得費加算の特例」が適用されることもあります。
Q.複数の相続人で1つの不動産を相続した場合、どのように管理すればよいですか?
複数の相続人で1つの不動産を相続した場合、相続人全員で協議して管理方法を決める必要があります。賃貸する場合や売却する場合も全員の同意が必要です。安易に法定相続分で相続せず、相続人全員で話し合いましょう。
Q.相続した空き家の処分方法を教えてください。
相続した空き家の処分方法には、売却、賃貸、解体などがあります。老朽化が進んだ空き家は維持費がかかるため、早めに処分を検討することが望ましいです。また、特定空き家に該当すると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる場合があります。
Q.相続した不動産に抵当権がついている場合、どうすればよいですか?
相続した不動産に抵当権がついている場合、そのままでは売却や担保設定ができません。抵当権の抹消手続きを行うか、借入金の返済を行う必要があります。債権者との協議を通じて対応方法を決めることをお勧めします。
生前対策
Q.生前贈与のメリットとデメリットは何ですか?
生前贈与のメリットは、相続税対策になることです。毎年一定額(年間110万円まで)は贈与税がかからず、長期的に贈与を行うことで相続税の負担を軽減できます。また、家族間の財産の移転が生前に行えるため、円滑な財産承継も期待できます。 一方、デメリットは贈与の都度、基礎控除を超えた場合、贈与税の申告が必要なことや、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、思ったよりも節税効果が得られない場合があることです。
2024年1月1日以降に贈与される財産については、対象期間が順次延長され、最終的には相続開始前7年以内に行われた贈与が対象になります。
Q.遺言書の作成方法と種類を教えてください。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
自筆証書遺言:遺言者がすべてを手書きで作成する方法です。費用がかからず手軽ですが、形式不備や紛失のリスクがあります。
公正証書遺言:公証人の前で作成し、法的な形式が整っているため無効になる可能性が低いです。作成には費用がかかりますが、安全性が高いのが特徴です。
秘密証書遺言:内容を秘密にして公証人に作成の確認をしてもらいます。存在を公証人が証明するため、紛失リスクは低いですが、遺言内容の有効性までは保証されません。
Q.家族信託とは何ですか? どのような場合に有効ですか?
家族信託とは、自身の財産を信頼できる家族に託し、将来の管理や処分を任せる制度です。認知症や判断能力の低下により財産管理ができなくなるリスクに備えたい場合や、法定相続人とは異なる相続を希望する場合に有効です。家族信託を利用することで、将来の財産管理をスムーズに行え、積極的な資産運用や資産の組み替えも可能になります。
Q.生命保険を活用した相続対策について教えてください。
生命保険は、相続税の納税資金や遺産分割対策として有効です。生命保険金は「法定相続人1人当たり500万円」の非課税枠があるため、相続税の負担を減らすことができます。また、受取人を指定できるため、現金をスムーズに相続人に分配することができ、遺産分割協議を円滑に進めることが可能です。
Q.認知症に備えた財産管理の方法はありますか?
認知症に備えた財産管理方法としては、以下の3つがあります。
任意後見制度:元気なうちに将来の財産管理を任せる人を決めておく制度です。判断能力が低下した場合に家庭裁判所の審判を経て後見が開始されます。
家族信託:財産を信頼できる家族に託し、信託契約に基づいて管理・処分してもらいます。
成年後見制度:家庭裁判所が選任した後見人が財産管理を行います。判断能力が低下してから利用できる制度で、本人の利益を法律的に支援する制度です。
事業承継
Q.事業承継の準備はいつから始めるべきですか?
事業承継の準備は、早ければ早いほど良いとされています。目安として、少なくとも5~10年前から準備を始めることが推奨されています。後継者の選定や育成、事業計画の見直し、税務・法務面の対策など、時間をかけて進めるべき事項が多いため、早期の着手が成功のカギとなります。
Q.後継者が決まらない場合、どのような選択肢がありますか?
後継者が決まらない場合は、以下の選択肢を検討することができます。
1.社内の幹部社員への承継:親族外の従業員や幹部社員を育成し、事業を引き継ぐ方法です。
2.M&Aによる外部承継:第三者に会社を譲渡することで、会社の存続と従業員の雇用を確保します。
3.廃業または清算:後継者が見つからない場合、会社の清算を検討することもあります。事業を整理し、資産を売却して債務を返済するプロセスを経ることになります。
Q.事業承継税制とは何ですか? どのような優遇措置がありますか?
事業承継税制とは、後継者に事業を引き継ぐ際の税負担を軽減するための特例制度です。具体的には、事業承継で引き継ぐ株式に対して相続税や贈与税の納税を猶予または免除する措置があります。要件を満たせば、後継者が事業を続ける限り、納税が猶予され、最終的に免除されることもあります。
Q.親族外承継を考えています。注意点は何ですか?
親族外承継には、社内の幹部社員や外部企業への譲渡などの方法があります。注意点としては、後継者の選定基準や、従業員や取引先に与える影響、企業文化の継承、税務対策の見直しなどが挙げられます。特にM&Aを通じた承継の場合、買収側の意向と現経営陣の意向を一致させることが重要です。
Q.事業承継に伴う従業員への対応はどうすればよいですか?
事業承継時には、従業員の不安を解消し、理解と協力を得ることが重要です。まず、事業承継の方針や後継者の情報を適切なタイミングで説明し、承継後の経営方針や従業員の処遇が変わらないことを伝えることが大切です。従業員との信頼関係を維持するために、継続的なコミュニケーションを行い、承継プロセスに積極的に参加させることも有効です。
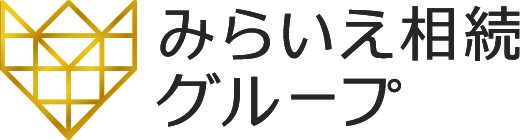



 0120-957-339
0120-957-339